ホーム
66フォロー
201フォロワー



Notionが、全スタートアップに「無料枠」を開放する理由
岩崎 雅也キッズプログラミングスクール8x9(ハック) 執行役員
Notion、以前からがっつり業務で使ってますがITエンジニア視点から見てもこれほど痒いところに手が届くナレッジ共有ツールは今までなかったというぐらい重宝してます。ここ10年で色んなWebサービス見てきた中でも個人的にはGmailやGoogleMapが世に出てきた時並みのインパクトに思えます。
特筆すべきはUI/UXでIT畑にいない事務スタッフさんですら自分でページをカスタマイズして使えるほど直感的で優れています。多くのグループウェアは機能ごとにUI/UXが異なり学習コストが膨らみますがNotionはそこが最小限に抑えられてます。
一方で、他の方が仰るようにこのグループウェアはこう使うべきという型がないので、あらかじめ企業毎に使い方をデザインする必要があります。ので、運用設計するコストは高めですがそこさえ決めたら自分達が望む最適な使い方が作り出せるのが魅力です。
年々ページの使い方が効率化していき自分達で育てていくグループウェアって感じが面白いです。
親の「公立離れ」を招いた私立とのオンライン授業格差、学校と教師に募る不信
岩崎 雅也キッズプログラミングスクール8x9(ハック) 執行役員
オンライン授業が神格化されてる気がします。
義務教育は暗記反復で身につく分野が多いからプリント配布がそこまで悪いとは感じません。
オンライン授業190コマ以上実施した経験で言うなら、環境面に加えて双方向、少人数、指導者と受講者のITリテラシーが揃わないとまともに機能しないです。
それこそ今の学級編制でやったら授業困難、環境トラブルで親や支援員が横で張り付き必須なのは容易に想像が付きます。
加えて勉強できる子は方法問わず自分でできるから、オンラインで何かするとしたら成績不振な児童のエンパワーメントだと思っています。
ただしこれは学校や教員に一方的に押し付けるものではなく親が自責と捉えないと、いつか子供が壁に当たった時に愛する我が子を理解しようとせずに他責にしてしまう恐れがあります。

【解説】人気沸騰「Dispo」が示す、写真SNSの新しいカタチ
岩崎 雅也キッズプログラミングスクール8x9(ハック) 執行役員
コンセプトや利便性云々の前にSNSの新陳代謝は年々早まっていて、主に世代間(若者の飽き)で起きるのでそういう文脈もありそう。
正直おっさんの僕からすると、
・レタッチを排除(盛れない写真)が時代を逆行してて理解不能
・すぐにプレビュー&シェアできないことが時代を逆行してて理解不能
・写真撮ることに集中できるUXとは言うけど、僕的にはSNS用に奇跡の1枚が撮れるか否かの方がその場ではスッキリする(撮れたら後は写メ撮らない)
・そもそもこの仕組でマネタイズどうするんだろうという謎
と旧世代の思考だと良さが理解できません。
でも昔のカメラの不便さを知らない若者や、今の完成しきったSNSに新鮮さを感じない層には違ったコンセプトの方が刺さるのかなぁと思います。
「個」の時代がやってきた。教育はどうあるべきか
岩崎 雅也キッズプログラミングスクール8x9(ハック) 執行役員
個別最適に加えて能動的学びなのか受動的学びなのかもポイントになりそう。
傾向として子供が求める学びは今目の前にある興味関心で、大人が求める学びは将来役に立ちそうか否かを基準にする事が多い気がします。(子供は投資の考え方や社会経験がまだ少ないから)
でも実際のところは興味関心から来る学びは、能動的且つ非効率に進むから独自の経験が積み上げられ理解も深く専門性を帯びやすいし、一方で将来役に立つ云々は安牌だけど不安解消ビジネスに利用されやすくパッケージ化された学びだった場合は受動的且つ競争化しやすい。
親としては子供が何に目を輝かせているかを観察しそれがどんな投資になるかをマネジメントしてあげる能力が必要になってくると思います。

NORMAL

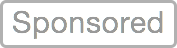











投稿したコメント