ホーム
84フォロー
11879フォロワー


当事者になる偶然と、当事者でいる意志について(3.11に寄せて)
中里 基NewsPicks 執行役員 CFO / CHRO
今年も3.11を迎えます。
東日本大震災から13年。当時の中高生は30代に差し掛かり、当時20代だった若手は40代に差し掛かる。全員が13年分年を取りました。
当事者になるのは偶然でも、当事者でい続けるのは本当に難しい。毎年この日だけ思い出したように震災を言うのも白々しくて、ちょっとここで書くのもやや迷いましたが、いやそんなことどうでもいいじゃないかと。つべこべ言わず年に1日くらいは、誰のためでもなく自分のためにでも福島に想いを馳せ、当事者であり続けたい。
3.11の共通体験が少しずつ希薄になる中で、今回のトピックスは自分にとっての記憶と記録を接続する、なんというか自分のためかもしれない記述です。

【初公開】年収1000万と800万円の「スキルの違い」10選
中里 基NewsPicks 執行役員 CFO / CHRO
今年の春先に出たBCGのExecutive Perspectives 「The CEO Outlook」を見ていたのですが、このP13にグローバル経営の最優先アクションはコスト削減であり特に業務効率向上というのが明確に出てきています。
経営アジェンダというニーズと、組織で求められる必要スキル(記事中でいうワークタグ)は、実にタイムリーに一致してくるものなんだなとも感じました。
一方で経営アジェンダとタイムリーになるスキルであるということは、この先流動的であることもまた間違いなく、普遍的にアンラーニングと学び続けることに謙虚でありたいとも思いました。
▼ BCG Executive Perspectives 「The CEO Outlook」(2023)
https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-CEO-Outlook-Survey-March-2023.pdf

NORMAL

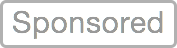











投稿したコメント