ホーム
2131フォロー
403フォロワー


OpenAI、日本を含む一部地域でChatGPT利用をサインアップ不要に
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
授業での利用に、サインアップ不要は非常にありがたいです。
以前、携帯電話の登録が必須でアカウント制限があった時には、学校配布のメールアドレスに紐付けさせると卒業後に私用アドレスに紐付けられる件数を食ってしまう懸念から、ログイン不要のbingAIを使わざるを得ませんでした。
年齢の規約や保護者同意などについては確認をしようと思いますが、情報利用のオプトアウトなどもできるのであれば、授業利用のハードルはものすごく下がるように感じますし、使い方の注意点なども指導がしやすいように思います。
AIツールは広告モデルには馴染まないため、サインアップ不要は一見収益に結びつかないようにも感じますが、裾野が広がることによって、結果的に有料サービスを利用したり、APIを活用するケースが増えることになるのではないかと思います。
あるいは、顧客を取り込んだ後に、関連した広告が表示されるようになってしまうこともありえるかもしれませんが……。
生成AIの消費電力、全人類のAIアプリケーション利用に必要なのは原発2基
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
この記事は、AIの消費電力の少なさを扱った記事だと思います。
AIのトレーニングは、誤差逆伝搬法で何度も勾配を計算しながら最適な重みづけを探索する探索過程で、これはそれなりに電力がかかるものの、一度だけの工程、
いわばイニシャルコストです。
一度トレーニングが済んだあとの推論過程は、学習した重み付けを用いてひたすら行列計算を実行するようなもので、トレーニングに比べると計算量自体は微々たるものです。
今回推定されたのが、このランニングコストが全人類が使ったとしても原発2基分、ということでした。
生成AIの生み出す生産性を考えると破格に少ないのではないでしょうか。
一流大の女子大生がデリへルで働くしかない日本の異常さ
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
現在、高等教育無償化制度の存在によって、非課税世帯の場合には授業料免除と給付の組み合わせで、一般的な文系私学の学費は賄える状態になっていますが、
給付を受けられないギリギリの収入がある世帯で、地方から出てきている場合には、記事のような状況に陥りやすいようにも思います。
その場合、勉学を再優先にするなら貸与の奨学金を受ける形になるかと思いますが、これは将来返済する借金になります。
記事では、都内での一人暮らしの生活費が20万、
貸与奨学金を12万限度額まで借りて、アルバイトをギリギリまで行ってプラス8万、とあります。
金額的にトントンなら水商売ではなくそれを選ぶべき、という声もあるかと思いますが、昨今ブラックバイトの問題もあるように、余裕のない生活の中で学生が学業よりもアルバイト先の要望を優先してしまうのは、こうしたギリギリの生活と無縁ではないようにも思います。
また、この計算だと、学費は保護者が負担してくれているのかもしれませんが、それも滞る可能性もあるかと思います。
家計を考慮して就職の道を選ぶ生徒もいました。
何がなんでも大学に行くのが良いとは思いませんが、
無償化の条件を高等学校の就学支援金と同程度にするか国公立だけでもかつてのような無償に近い学費で、という方向性は必要のようにも思いますが、それは現実的でしょうか。
現在の大学生の人数は、約300万人のようです。
1人あたり100万円かかると考えれば、専門学校生なども含めると3兆円以上の財源が必要になりますが、これは消費税でも上げない限りは難しいように思います。
一方で、国公立大学の在籍者は40万人程度なので、毎年2500億円程度の予算があれば無償化が可能かと思います。
「経済的に苦しい場合には、国公立に行け」というのが正しいあり方かどうかわかりませんが、そもそも、大学に行って学ぶことが国と個人にとってどんな意味を持つのか、考える必要があるのかもしれません。
ここで使った財源が、国や個人の豊かさに直結するのであれば迷わず使うべきなのかもしれませんが……
VRは恐怖症の克服に革命を起こす--なぜ普及が進まないのか
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
恐怖症の克服には、安全な環境下で類似の刺激に馴れさせていく曝露両方が有効です。
私も、特定の教室に入れない生徒や学校に来れない生徒に、「どこまでなら入れるのか」「誰と一緒なら入れるのか」「何が不安のもとなのか」などの条件を確認して、付き添いをしたり、座席の調整をしたり、人が来る前の教室で予行練習をするなどの方法で対処しています。
この際重要なのは、
「不安感のない状態で試す(お気に入りの音楽などで気分を上げた後なども有効)」
「段階的に刺激の強度を上げる」
ということです。
幸い、勤務校では、勇気を振り絞って行った先で嫌な思いをすることが少ないようで、何とかこうした対処がうまくいっています。
恐怖症は、自分でもコントロールできない無意識下で刺激と恐怖心が結びついてしまっているため、それを緩めるためには別の条件付けを形成するのが有効です。
ただ、病院等では、そうした刺激自体が用意できないため、曝露療法の治療では、宿題と言う形で、患者自身が実行するような形をとることもあります。
VRは、そうした難点を全てクリアできることができる極めて優れた方法だと感じています。
以前、面接に苦手の意識のある生徒に、VRゴーグルを使って面接練習をしてもらったこともありましたが、非常に効果的でした。
サムスンが翻訳スマホ 通話を同時通訳、まず英語など
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
生徒の保護者面談を通訳の方に来て頂いて行うことが多いのですが、手配できなかった時に翻訳デバイスを使ったこともあります。
通訳の方とデバイスの一番大きな違いは、通訳の方は、微妙なニュアンスの時に「質問」をして、話したい内容の意味を確定させてくれる点だと思います。
また、会話や対話にはエネルギーの交換としての側面もあり、説得力や信頼感を与える意味でも、デバイスはタイムラグが大きく、不利な面があると感じます。
内蔵チップで翻訳をした場合に、クラウドよりも即時的な反応が得られるのではないかと思いますが、ここから先の翻訳デバイスには、単純な精度そのものに加えて、何かしらの体験の質が求められてくるように感じます
漢字にもっとふりがな振って マネックス松本氏が活動
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
勤務校では外国に繋がる生徒が多いので、
形態素解析のmecabとVBAを組み合わせて、word文書に自動でルビを振るマクロを作成し、それを職員で使用しています。
固有名詞は、個別の辞書用ファイルを作って読み込ませる仕組みにしています。
フリガナのあるなしで学習の効率や取り組みは大きく変わるのも確かです。
ただ、この問題、意外と難しい課題が横たわっています。
固有名詞に対しては、辞書登録をしておくことでかなりの部分の対応はできると思いますが、個人名についての完璧な対応は原理的にできないものです。
「月」と書いて「ライト」と読む場合と「ルナ」と読む場合とを区別するのは、文脈でも判断できないからです。
ルビ振りは、形態素解析を使えば95パーセントくらいはうまく行くようにつくれますが、完璧なものを作るのが難しく、
最後の完璧性を期すためにかなりの労力(人力)が必要、という点が、ルビの問題を簡単ではないものにしていると思います。
今回のサービスがどのようなものになるのか、楽しみです。
花粉症被害軽減へ花粉発生量を30年で約半減へ 政府関係閣僚会議で対策全体像まとまる
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
娘とともに舌下療法中です。
1年が経過したところですが、今年の花粉はキツイと言いますが、平年以下ほどの症状に収まりました。
舌下療法は、数年単位で毎日、花粉を含んだシダキュアという薬を口の中に1分入れておくことで、花粉に慣れさせる療法です。
毎日の投薬は、慣れればなんてことはないのですが、月一の通院が数年単位で続くのはそれなりに大変です。
医療はそういうもの、と言ってしまえばそれまでですが、さらっと見て異常がなければ薬が出るだけ、という状況なので、リモート診療+薬を郵送などの方法が可能になればもっと治療を受ける人が増えるかもしれないとも思います。
24年卒、企業の採用環境悪化=応募少なく人手不足―リクルート調査
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
本校の進路決定率は10年前50%程度でしたが、
様々なアプローチを行うことで、8割以上の生徒が進学か正社員での就職をできるようになりました。
コロナ禍の真っ只中だった年も、全体の求人が落ち込んでいたわけではなく、接客や飲食、宿泊等の特定の業種が特に落ち込み、また、打撃を受けた製造業の企業とそうでない企業との間で、採用意欲がまるで違うという状況でした。
近年は、
製造、物流、介護、ガソリンスタンド、建設等の企業にお世話になることが多く、マッチングさえ合っていれば、待遇も良く、定着も良いと言う印象です。
恥ずかしい話ですが、定時制で進路を担当して初めて、生徒の職業への適性について考えました。
進学校では、何をやりたいのかよりも、苦手な科目を避けることの方を優先することが多く、数学が苦手なら文系と言う観点で文系に進むケースが多いように思います。
そうした中にも、対人サービスよりも製造に適性があるという生徒は多くいるように思います。
今、進路指導する際には、最初に、「人相手の仕事」をしたいか「もの相手の仕事」をしたいかと聞きます。
進路の環境を改善するために本校では
キャリアデザインという授業を作って1年生全員に履修させることで進路意識を高め、
校内で企業説明会を実施することで、外部の人間と接することの不安感を払拭し、
職業訓練校や企業への校外学習、インターンシップを実施することで、様々な職業や自分自身の興味について理解を深めています。
対人での不安を持つ生徒に対しては、見学への付き添いを実施することもありますが、そうした生徒も、いちど不安が取り払われると問題なく試験を受けられ、仕事もこなせるケースが多く、ちょっとした支援がその後の人生を大きく変える可能性を感じます。
20年後に"食える子"の親は今何をしているか経営学者が示す食いっぱぐれないための"最低限のスキル"
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
自己決定力を身に付けることは、非常に重要だと思うものの、
日本の学校教育では苦しい思いをする懸念があります。
自分の意志や希望を強く持てば持つほど、衝突せずにはいられません。
以前、モンテッソーリ教育の小学校を視察したことがありますが、そこでは、時間割に囚われずに各々が自分でテーマを決めて、興味の向く「お仕事」を突き詰めていました。
教具とその使い方によって一定の枠がありながらも、教えこませることはせずに能動的に学習をするその空間を目の当たりにすると、
通常の教室は、決められた時間枠に自らを順応させ、教師の話の中に何とか動機づけを見つけて、お仕着せの学習内容や社会規範に溶け込んでいく場所です。
誰も、今日は何を学習したい?
とは聞いてくれません。
ですが、スマホやAIにサポートされることで知的能力が増強された人間にとって重要なことは、何をしたいか、という意志なのは間違いありません。
水素があれば「ロシア依存」から抜け出せる欧州が着々と進める次世代エネルギー戦略のしたたかさ
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
その水素をどうやって調達するのか。
結局、化石燃料を元にしたグレー水素やブルー水素が安価なのでは、と思わずに要られません。
と思って調べてみると、
「グリーン水素のコストは1kgあたり3~8ドル程度で、天然ガスから製造するグレー水素の0.5~1.7ドル、ブルー水素の1~2ドルを上回っています。」
https://www.asahi.com/sdgs/article/14677144
となると、天然ガスから製造するのが最も安価で、結局、脱ロシアをするより、ロシアからガスを輸入して水素を作る方が良い話になってしまいます。
天然ガスも石油も、掘れば勝手に噴き出してきて、経済性が圧倒的に高いことがポイントなのではないかと思います。
とはいえ、再生可能エネルギーが化学エネルギーに添加された形で安定的に運べるなら、可能性はあるようにも思えます。
重要なのは、風力や太陽光、地熱などを利用しやすい地域から、安定して水素を固定化し、運ぶことのできる仕組み作りだと思います。
現状、液体水素は極低温、高圧下に保存しなければならず、危険性もあります。
トルエンやアンモニアなどを水素キャリアとするアイデアはありますが、何か大きなブレークスルーが必要で、それはまだ起きていないように思われます。
日常生活で「ChatGPT」を活用するヒント5選
佐良土 賢樹定時制教諭(物理・情報) 公認心理師
高校の物理の問題で、方程式を使わないものは大体解ける印象です。
プログラム生成は特に素晴らしく、有名なライブラリの使い方を学習するための100本ノック系の問題集は、ほぼ正確に解けました。
ただ、知識面はかなり怪しくて、オリオン座を夏の星座だと言ったり、アポロンがオリオンを特に慕っていたと言ったり、(アポロンは、妹のアルテミスを騙してオリオンを殺すように仕向けている)、鵜呑みにすると危険な返答が多い気がします。
メールやプログラム生成みたいに、「自分で作ることもできるけど、時間がかかってしまうものを時短で」という用途が適していているように思います

NORMAL

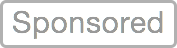











投稿したコメント