ホーム
2472フォロー
659フォロワー


第2、第3の自民党・政治資金パーティー事件を暴き出すのはもはやAIか、政治家の汚職や不正もAIが見抜く時代に 【生成AI事件簿】米国で登場した、政治家のインサイダー取引を見抜くAI
澤 俊樹なし なし
NHKのドラマ「17才の帝国」はAIが17才の高校生が総理大臣指名し、斜陽の日本を救おうとするものでしたが、なぜかAIが人間社会の矛盾を救ってくれるかもしれないと思ってしまいました。
ほんの一握りの人々はますます豊かに、そして多くの人々が貧困化していくのは、テクノロジーが一役買っているからでしょう。
でもテクノロジーとしてのAIが、権力の奴隷ではなく、国民全体の幸福のために使われるユートピアがあるとしたら、AIが政治家たちの腐敗を暴き出し、既得権益を破壊していくことを、最初に始めるかもしれません。
メディアが民衆のためのジャーナリズムを放棄して、政府の広報機関のような現在、こんなAIに登場してほしいと思ってしまいます。
AIのアルゴリズムに対する疑念を払拭できないとしても、隠されている不正を暴き出していけば、不正は行われなくなって、政治の透明性が腐敗を防止してくれるでしょう。
それでも人間社会の矛盾や不幸が完全になくならないとしても、ゾンビ化した既得権益と一体化した政治を克服しない限り、日本はますます貧困にるでしょう。
そして私たちは、もっと人とのアナログ的な繋がり、困っている人を助けたいという気持ちに基づく行動としての繋がりによって、心豊かに生きるべきなのでしょう。これはAIではできないことなのですから。
「トヨタとは逆を行く」、ホンダのハイブリッドシステムは1本に集約
澤 俊樹なし なし
トヨタとホンダが同じハイブリッド車でも、モーター(電池)とエンジン(ガソリン)の最適解が違うということなんです。
トヨタの電動車のマルチパスウエイ戦略が、EV/PHV、HV、FCVというだけでなく、さらにHVのマルチパスウエイを落とし込んでいるということです。
つまり、燃費のいいHV(環境重視)だけでなく、ガンガン走るHV(ガソリン車並の走りにシフト)、そして高級車ごとに、モーターとエンジンの使い分けをしているのです。
それに対しホンダは、スポーティな走りを味わえるハイブリッドで中国で売れなかったという反省もあるのでしょうが、最終的にEVに近い2モーターの「e:HEV」に集約したんだと思います。
EVモードで電気のみで市街地を、HVモードで加速時などではエンジンを稼働させ、さらに高速ではエンジンのみで走るという、その時々の走りに合わせたモードになっているのは、e:HEVです。
高速道路を走る時はモーターに負荷がかかるので、ガソリンのみを稼働させ、追い越しや坂道などではHVモードをちょこちょこ稼働させて(ついでに電池に充電)電池の残量を減らさないようにするという、EV寄りのハイブリッドなのです。
ソニー・ホンダのEV「AFEELA」がまるでスマホのようなエンタメ空間を演出する車であるのに対し、ホンダのe:HEVは脱エンジン車のつなぎの車としてスマホと繋がる利便性を持たせていますが、ホンダが独自のEVをどのようなコンセプトで展開するのか、ハイブリッドを集約していくe:HEVもエンジンの使い方については若干マイナーチェンジがありそうです。エンジンとモーターがどういうふうに配置されているか、歯車まで関心があるマニアックな人には、このトヨタとホンダの違いは興味をそそるのではないでしょうか。
電力会社の送電容量を40%増強するノルウェー企業の「マジックボール」
澤 俊樹なし なし
カルフォルニアでは、送電線が樹木に接触して山火事が発生し、大手民営電力事業PG&Eが伐採するなどの対策を取らなかったして住民から訴訟を起こされ、破綻しています。
6年間で1500件もの山火事が発生し、住宅地域への延焼で多数の住民が死亡しています。これには地球温暖化と森林伐採による空気の乾燥も影響しています。つまり電力需要の増加と高温で送電線が垂れ下がり、乾燥した樹木に接触して山火事になったということなのです。
Heimdall Powerの“magic ball"トイセンサーは、送電線の温度、電流、角度の送電線データと、Meteomaticsのドローンで収集された気象データとを機械学習させて、送送電容量を増強できるようにしているものです。
これはDLRと呼ばれるもので、アメリカではLineVisionが送電網用のセンサーでサービスを展開しています。丸紅も同社に出資し、日本代理店となっています。
また住友電工が北海道電力ネットワークと 架空線ダイナミックレーティングシステム導入に向けた実証試験開始しています。
送電線を静的な定格容量と実際にどのくらいの容量があるのかという運用容量は違っていて、「送電線に流せるのは設備容量の50%まで」というのは静的な容量です。
DLRは外部環境の変化に合わせて実際に流すことのできる電力容量を増加させる技術です。
再エネの普及を一層進めるためにも送電網の増強を伴わないDLRは、望ましいと考えられます。
>動的線路定格 (DLR:Dynamic Line Rating) という柔軟で「賢い」考え方
2019年4月18日 安田 陽 京都大学大学院経済学研究科特任教授
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/occasionalpapers/occasionalpapersno123
抜粋)「送電線に流せる電力は設備容量の50%までに決まっている!」というネットでよく見かける議論は極端な例ですが、従来の簡易パラメータのみの静的な計算では安全率を不必要に過剰に見積もらざるを得ず、これではコンピュータがなかった昭和時代のやり方を踏襲しているかのようです。
著書:「送電線は行列のできるガラガラのそば屋さん?」
中国にEV墓場、テスラ株は暴落…「やっぱりトヨタが正しかった!」と浮かれる人が見落とす死角 - 今週のキーワード 真壁昭夫
澤 俊樹なし なし
HVの爆売れに浮ついている暇なんかないですよ、という忠告です。
マルチパスウエイ戦略が試されるのは、好調なHVに注力しすぎないようにということなのだと思います。
今こそ次世代電池の開発に資源を投じることやモビリティサービスの会社として脱皮すべきだと思います。
競業自動車メーカーとも連携し、モビリティデータやさまざまな個人の趣向まで含めた膨大なメタデータビジネスで巨額な利益を得ようとする巨大IT企業との競争に備えなければならなのです。
そうでなければ自動車メーカーは巨大IT企業の下請けでしかなくなり、生き残るのはスマホ製造の鴻海のような巨大受託製造業者だけになるからです。
つい先日日産のHVがスマホと繋がっていることにちょっと驚きました。
HVもテスラ化していくんですね。
そう考えるとマルチパスウエイ戦略は、ユーザー目線ではあっても、未来の顧客創造戦略とは言えないと思いました。
英紙が評価 トヨタのハイブリッド車を推す戦略は正しかったのか? | 批判していたアナリストも「トヨタに謝らなければならない」
澤 俊樹なし なし
今のHV車がスマホで運転情報や燃費などを教えてくれる車種もあるんですね。
HV専用エンジン開発も活発となってきていて、BYDのようにEVとPHVのメーカーは、ガソリン車より安いPHVを出していますが、そのPHVのエンジン効率は非常に高いです。
PHVも長距離優先か街乗り優先かでエンジンとモーターの使い分けを自動車メーカーはしているようです。
電池で街乗りするユーザーがどのくらいいるのか分かりませんが、ガソリン車より割安だったら、そりゃユーザーは飛びつくでしょう。
最も欧米の事情は違うでしょうが、マイルドハイブリッドを販売している欧州メーカーが、プリウスのようなストロングハイブリッドにシフトするのかどうか、本記事は触れていません。
つまりHVが売れているのは確かなのですが、エンジンをストロングハイブリッドにシフトしようとするのかは、見落としているような気がします。
ちなみにBYDのPHVは、プリウスと同じスプリット方式のハイブリッドです。
自動車メーカーがHVの専用エンジン開発とハイブリッドの方式の選択に注意していきたいところです。
製造業だからできる技術と構造の革新。アイシンの「ものづくりの力」を探る
澤 俊樹なし なし
アルミ溶解をガス炉から電気炉に変更できれば、脱炭素も、再エネ由来の電気を購入すれば済みます。
でもガス炉で排出される炭素を利用するメタネーションを選択したというところが、アイシンが自社技術を徹底的に活用する挑戦を選択したということだと思っていました。
ガス炉の高熱を利用して高効率な高温水電解の活用も視野に入っているんでしょう。
デンソーと同じような方向性で技術開発を競っているようでもあるようです。
炭素経済社会がもし訪れてきたら、炭素を削減するより利用する炭素循環は、強力なビジネスモデルになるはずです。
製品の性能やコストが差別化の要因だった時代はもう過去のものになってきているんですね。
森永卓郎×森永康平 親子で語る庶民の暮らしがよくならない「最大の原因」「格差の元凶」
澤 俊樹なし なし
日本経済の「デスノート」・・・
大国に貢ぐ「朝貢国」となった日本。
しかも貢ぐだけで、恩恵は庶民には決して巡ってこない。
国家との関係にとどまらず国家以上に巨大な巨大テック企業に、スマホのタップ一つ一つがデータという貢物を私たちがしている訳です。
政権が変わってもこの構造は変わらないと諦めてしまっている人々が多くなればなるほど、格差が拡大するパワーは大きくなるようです。
権力の世襲から目を逸らせられていることに、「ジャーナリズムは死んだ」と日本で経済アナリストの森永卓郎氏が、朝貢国の行く末を警告されているのではないでしょうか?
裏金問題より遥かに大きな国民を裏切る「亡国」の巧妙な見えない罠を暴いたのは、ステージ4故でしょうか。。
シャープ、液晶事業縮小へ 不振の堺工場、生産停止を視野
澤 俊樹なし なし
「液晶の次は液晶」と巨額投資をした堺工場です。
「畳プロジェクト」の責任者が次期社長となり、自信満々で推し進めた「クリスタルバレー」と称された堺工場でしたが、もうその頃は中国のBOEが力をつけ始めていて、マザーガラスも堺工場より大型化に成功し、それどころか製造ラインの本数も、世界の需要を賄えるほどではないかと思えるほどでした。
PDPと液晶が薄型TVでどちらが勝つかという争いが、40インチで綱引きしていた過去は、液晶が1インチ1万円を下回れば勝ちというような話で盛り上がっていました。
そういう時代に液晶で「世界の亀山モデル」と売れた訳ですから、「液晶の次は液晶」という錯覚もしてしまったのでしょう。
シャープは液晶の生産ラインをソニーの要求を満たすほどに割り当てず、自社向けでフル生産していました。さすがにソニーも、平面CRTのTV、ブランドは「トリニトロン」に執着した苦い経験から、シャープから液晶パネルを手に入れたかったので、韓国から調達するように舵を切りました。そして巨額投資した大型ラインが空き始めてしまったのです。
当時巨額投資を礼賛する提灯記事が目につきましたが、もうその時にはBOEが研究開発投資を大胆に行っていて、大型マザーガラスの量産ラインを構築し始めていたのです。
2009年にマザーガラス10世代の生産を世界で初めて開始したシャープでしたが、2015年にBOEに技術供与をしました。そして2019年にBOEは世界一の液晶パネルメーカーとなったのです。
驕れる者久しからず。
まさに日本の凋落の根源にある精神ではないでしょうか。
「結婚を避け、子供をもたない」ほうが人生のコスパが良い…現代の日本人に起きている"憂慮すべき変化"
澤 俊樹なし なし
結婚や子どもを持つことは、コスパやタイパが悪いからではなくて、貧困化する日本という時代が、結婚に踏み切れなかったり子どもを持てないことにつながっているのだと思います。
資本主義による人間の家畜化は、資本主義の失敗だとも言えます。資本主義がこれかも成長するには、人口減少は大きな障害です。だからすでに資本主義は失敗しているのです。
東京はこれから富裕層しか住めない都市になっていくでしょう。そしてその富裕層の暮らしを支えるエッシャンシャルワーカーが、その周辺に暮らす二極化した都会の姿がはっきりしてくるでしょう。
アメリカではエグゼクティブのような多く稼ぐ女性はちゃんとしたパートナーがいて、子どもも二人三人といるようになってきました。ただ結婚はビジネスキャリアを積んで高収入となった30代だということらしいです。
手が掛かる子育てはベビーシッターを雇ったり、やパートナーの協力などもあるとのことです。
(文化的な背景もあるとは思います)
資本主義が本当に正しいのか、ほんの一握りの人だけが豊かになって、ほとんどの人々が貧しくなるとしたら、資本主義は未来をどうしていくのか、そろそろ真剣に考えた方がよさそうです。
多くの人々は分断され、矛盾が生み出す不満や怒りが隣の貧しき人に向かうような仕組みに、気づかなければ、私たちには資本主義の失敗は見えないでしょう。
NECがデータセンターの売却検討、最大740億円-22年ぶり高値
澤 俊樹なし なし
NECのデータセンター事業は、SIやアウトソーシングを含めた事業を行うSIer系、クラウド事業者などとのコネクティビティ機能などを強化しているとのことです。
それというのも、「SIer系事業者に共通しているのは、ビジネス規模が大きいものの、成長率が低いという課題がある点だ。その一方で、コネクティビティを強化した専業系事業者は、高い成長率を維持している。当社はクラウド事業者などとのコネクティビティを強化することにより、成長率を高め、事業を拡大していく方針を打ち出している」とし、成長領域をクラウドHubDC(メガクラウド事業者との接続性を重視したデータセンターとして展開)と定め、「クラウド基盤とのハブ機能を提供し、同社が推進するインターコネクテッドエコシステムの形成や、エコシステムパートナーとの接続をシームレスに実現する」と説明しています。(括弧内は参照記事より引用)
そのHubDC運用する適地は、「クラウド事業者が集中する印西エリアにDCを持つことは有効だ」ということですが、印西に土地や建物を所有していなかったので、SCSKと協業したということです。
そのデータセンター事業を売却するというのは、おそらく想定しているであろう「次世代のAIデータセンター」事業まで手放すということまで意味するのかどうかは、今後の動きに注目したいところです。
参照)
新局面迎えるNECのDC事業 多様なニーズに応える戦略を展開 2023/10/05
https://www.weeklybcn.com/journal/feature/detail/20231005_200563.html
NECが「NEC印西データセンター」を公開、最新のデータセンター事業戦略を説明 2023年7月20日
https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/special/1517452.html
ビル・ゲイツらも出資、「CO2を出さない」製鉄企業Boston Metal
澤 俊樹なし なし
Matsunaga さんが関心を持たれている金属棒=電極は高熱と高温に耐えることができる組成が大きな鍵を握っているようです。
webではクロム合金の一種と記載された記事もありますが、ほとんど内容は分かりません。
反応炉のサイズも不明です。
実験炉から新型のリアクターも開発して、ブラジルで商業展開に移ってきています。
鉄鉱石が豊富なブラジルで、コークス不使用で安価な粗鋼生産ができれば、製鉄業界に大きなインパクトを与えるでしょう。
水素還元鉄や電気炉によるグリーンスチール生産が始まろうとしていますが、低品質な鉄鉱石から粗鋼が生産できれば、次はいかに高品質な鉄鋼が生産できるかという話になります。
高炉も廃炉になっていく近い将来、製鉄業界はグリーンスチール生産への投資の選択次第では、業界から消えていくということになるかもしれませんね。
BostonMetal
https://www.bostonmetal.com/green-steel-solution/
米アカデミー賞、日本の2作品受賞 長編アニメ賞に宮崎駿監督「君たちはどう生きるか」、視覚効果賞に山崎貴監督「ゴジラ-1・0」
澤 俊樹なし なし
宮崎駿監督は「これまで本当の自分を曝け出してこなかった。今回作は自分の内臓を見せる」というような覚悟とも遺言ともとれる発言をしていたのをどこかで読んだ気がします。
記憶違いを承知で、「君たちはどう生きるか」の脚本に打ち込んだ宮崎監督は、自分自身の生涯を、その根源である少年時代をもう一度生きようと苦悶したとすると、受賞の誉より肩の荷を下ろした安堵感の方が優ったのではないでしょうか。
誰にも見せたくない、遠く暗く苦しかった少年時代をもう一度生きようと決めたのは、今の時代の息苦しさを若者たちに、逃げず誤魔化さず、正しい人間として生きよ、という応援歌を作らずには死ねないという気持ちだったのではないでしょうか?
アオサギの正体が何であれ、メッセージは受ける側の「これからの未来」をどう生きるかを探る旅に若者達に出るように促しているように思います。
映画の本編を観ることもなく語る恥ずかしさはありますが、残りの時間が短くなればなるほど、「君たちはどう生きるか」を自分自身に問いかけずにいられないのです。
大人たちに死ねと言われて育った軍国少年の記憶が今の若者たちを「正義の戦争」に駆り立ててはいけないという自分への怒りとなって、本映画の見えない底に流れているように思えるのです。
三井E&Sが世界初、大型舶用エンジンで「水素燃焼運転」成功
澤 俊樹なし なし
LNGを主燃料とする大型船舶に取り組んでいる一方で、更なる脱炭素、つまりゼロカーボン輸送船開発の一環のようです。
水素100%燃焼の大神船舶エンジンの開発が進んでいるんですね。
アンモニア焚き大型船舶エンジンもMANが開発しているところですが、水素焚きも手掛けていたとは。
まだ先の話ですが、水素製造船の開発にも取り組んでいて、洋上で水素を船舶の巨大な帆に受ける風を利用してタービンを回して、海水淡水化して水電解してグリーン水素を製造するという挑戦です。
風が弱い時は燃料電池も活用して、水素を需要地に運ぶというものです。
大型輸送制、水素製造船と言い、脱炭素に大きく舵を切ったんですね。
アップル、EV開発計画を白紙に-10年がかりのプロジェクト断念
澤 俊樹なし なし
スマホ化するAppleCarに投資するより、生成AIにすぐさま投資しなければ、Open AIに負けてしまうという焦りからでしょうか。
自動運転EVのデータもスマホの延長上にあるより大きな市場を想像するでしょうが、それより遥かに生成AIが生み出すビジネスは大きいトイことなのかもしれません。
Open AIはハードの半導体製造にも向かいつつあるとすると、その AI半導体を製造できるのは、TSMCなどごく限られた企業しかないでしょう。
その製造ラインをいち早く抑えなければ、 AI半導体を入手できないという極めて大きなボトルネックがあるということに、Appleは既に投資した数千億円ものカネを捨ててもいいと判断したのかもしれません。
AppleCarの販売のハードルの高さではなく、生成AI競争に1日遅れただけで、AI半導体の入手が絶望的に遅れる、つまりたった半年遅れても、もう船は出た後というビジネスだということなのでしょう。
日本がNVIDIAの企画学習用の高性能半導体のチップやモジュールを入手しづらくなっているだけで、生成AIの大きな世界的なムーブメントに乗り遅れてしまっているという国家戦略にさえ影響する状況を考えると、AppleのEV断念の判断はもっと早くに行われていたように思わざるを得ません。ティム・クックの判断は早かったのだと思います。
人口7割のドイツにGDPで抜かれた日本「世界4位で騒ぎ過ぎ」と語る人たちが分かっていないこと
澤 俊樹なし なし
日本が世界経済に対する地位の低下を象徴しているのかもしれない、そんな現実を直視しなければ、負け犬の勇ましい遠吠えにしか過ぎないのでしょう。
円安誘導、超低金利政策、大企業減税とセットとなった消費税増税、官製相場のような株高、これらは既得権益を利する政策とは言えまいか?
だとすると生活は少しも楽になっていないのに、株高で景気がいいと思ってしまうのは、もう多くの庶民は錯覚だったと気付き始めていると思います。
安い日本の観光地の極端な物価高が、地域に暮らす人々の暮らしをも脅かしているのではないかというニュースにも度々接します。
またGDPは貿易というモノやサービスといった、実態経済に結びついていますが、生成AIなどデータがますます巨大な資本主義の主役となっていけば、私たちが日々利用するスマートフォンなどのITデバイスが、ほんの一握りの巨大IT企業に集まるデータが、天文学的富の終着点になるかもしれないと、ちょっとデストピア的な未来を想像してしまいます。
私たちは便利なものに依存すればするほど、国力が落ちていく、そんなテクノロジーシステムに巻き込まれて行き始めている、そんな分岐点に立っているようです。
テレビを持たない若者たち--新たな体験で変化の兆しも
澤 俊樹なし なし
Appleのスマートグラスが登場したら、Z世代に限らず世の中はどう変化するでしょうか?
テレビとスマホというデバイスの違いとコンテンツの消費は、デジタルネイティブにとっては、その場の状況(一人で見るか、家族友人と見るかというような状況)によって選択が違うでしょう。
しかしスマートグラスの登場は、画面に流れるものを消費するということを超えて、ミラーワールドの世界が拓けるということに繋がると思います。
ニュースやバラエティ番組、映画、TikTok、Youtube、SNSがミラーワールドに取り込まれ、新たなサービスがそれらを駆逐していくか、統合していくということになるのかもしれません。
スマホが世界に登場する前とその後で大きく人々の生活が変わったように大きな変化を予想しています。
デジタル空間がリアル世界を飲み込むようなMatrixが起きるかもしれない未来を夢想しました。
既に実態経済より遥かに巨大化したバーチャルな経済が、極端な格差を生み出してしまった、文明の失敗をこれ以上繰り返して欲しくないと思うばかりです。
ルネサスの米企業買収、三菱UFJなどが総額1兆円の融資へー関係者
澤 俊樹なし なし
図研がEDAのSynopsysと提携して半導体の大きな動きであるチップレットにチャンスをつかもうとしているのとは、ルネサンスの狙いは違うようです。
EDAベンダーになるつもりではなく、GitHubのようなオープンなプラットフォームを構想しているようです。
柴田CEOの発言に「統合されたオープンなプラットフォーム」とあり、これまで買収してきた企業の技術も取り込み、かつて搾取され続けてきた車載半導体屋を脱却して、IoT、アナログ、次世代パワー半導体(SiC/GaN)の個別事業を統合して、顧客が注文する個別の商品をより高次元の部品ではないシステムとして顧客が開発していけるプラットフォーマーになろうとしていることではないか、そんな印象を持ちました。
そんな(リスクも当然ある)ビジョンに支援しようと金融機関も動いたのだとすると、柴田社長の人間力もあったのではないかと思います。
(どこかの「検討使」とは違いますね。)

NORMAL

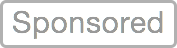











投稿したコメント