ホーム
12フォロー
124フォロワー


W杯「日本のジャイキリ」はデータ分析の賜物? Jリーグも取り込んだ「世界の潮流」とは
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
筆者です。カタールW杯連載の2回目となります。
日本等の各国のジャイキリは当然ながらデータ分析だけで成し遂げられたものではありません。しかし劣る個の力を補う”知力”は、サッカー弱小国でも科学技術や頭脳を駆使することで、比較的短期間に強国とのビハインドを埋めるツールになります。
欧州の強国などもデータ分析は当然やってきているわけですが、FIFAはその部分において各国に同等のレベルのインフラを用意し、弱い国でも同条件で知力勝負ができるように取り計らったことに高い意味があります。
喩えがマンガで恐縮ですが「ジョジョの奇妙な冒険」がパワー勝負の1-2部から、第3部以降スタンドによる知力勝負になって勝敗の景色が変わった、というのに近いと思っています。
また、その意味を理解して早くから国を挙げたアクションを取っていた日本サッカー界の努力が実った(実って良かった!)と考えています。
神戸イニエスタ契約2年延長 チーム「重要な記者会見」37歳誕生日に発表
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
少し思わせぶりな会見でしたが笑、喜んだサポーター・関係者の方が多かったのではないでしょうか。
Jリーグの歴史の中で、世界で名を馳せる外国人選手がもたらしたものはものは大きく、オンザピッチのプレーや戦術面、プロとしての姿勢といったに止まらず、オフザピッチでもサッカーの認知度向上や、スポーツ文化やプロスポーツ組織の在り方を、彼らが伝えてくれました。
現在、多くの日本人選手が欧州等で活躍したり、海外から優秀な監督や選手が日本代表やJリーグに来ているのも、長く日本のクラブに在籍し成果を出した「レジェンド外国人」たちが築いてくれた世界とのパイプが効いている。外国人選手の長い在籍によるリターンは、長い目で見た時にこの点が非常に大きい。
こういったレジェンド外国人は90年代~2000年代前半にプレーしていた選手に多く、近年は少ない中、イニエスタ選手がその仲間入りをしてくれそうなことに(今回の発表によって)、神戸のサポーターではない私もとても喜んでいます。
NASA、火星で酸素生成 「人類移住へ期待できる成果」
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
宇宙開発の大義名分の一つは、副産物として、極限環境を人間がコントロールしていくための技術が、地球上の社会産業のイノベーションにも貢献する可能性があるということ。
アポロ計画が生み出した技術的な副産物は、人々の生活を変えてきたものが多い。
昨今のSDGsの意識の高まりと、環境を克服するという宇宙技術の本質はシナジーがかなりあると考えています。今回の技術が、より発展することで気候変動対策の脱炭素化技術の加速に繋がるとより意義が出ると思います。
それはそうとして、大気の問題と、あとは放射線の克服に関わる技術イノベーションの萌芽が生まれれば、人類移住の現実感と注目度はグッと高まりますね。
日本宇宙ベンチャーを俯瞰して〜差はどこでつくのか?
NASAの有人飛行責任者がアルテミス月面着陸の2024年目標とクルー人選について語る
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
トランプ政権が月探査に振り切った背景には間違いなく対中国を意識した政策デザインの中で宇宙を位置付けた点が大きく、それで当初の予定を半ば強引に(予算の大幅増額とともに)前倒しをしています。
今月のサンプルリターン成功など、中国による月探査の加速が進む今、NASA側も大統領選の結果が出る前にアルテミス合意などの対中関係に影響を与える月面関連の施策の加速を進めています(バイデン勝利の可能性を見越しての、仕掛かり施策のクロージングを急いだものと見ています)。
決まっているNASA長官交代と新大統領によって、それがどこまで変わり得るのか(あるとしたらスローダウン)、1月以降の動きが非常に気になります。
「宇宙のガソリンスタンド」を目指すスタートアップOrbit Fabがシードラウンドで6.2億円を調達
日本人の月面探査に照準 JAXA予算、過去最高に
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
これは概算要求なので、結果がどうなるかは分からないのでミスリードのないよう冷静に見るべき。という前置きはつきますが、今までの概算要求と比べても前年との差分が非常に大きく、とてもインパクトフル。
増分の月面探査は、そもそもこれまで月着陸ミッションのSLIMとHTV-X開発を除くと、殆ど予算がついてこなかったので、むしろ問題を感じるくらいでした。(HTV-Xとて月専用の宇宙機ではないので、月の予算=SLIMという状況に近かった)
月面探査には日米外交上の米国からのプッシュという後ろ盾もあり、財務省を通すに十分な説得力があると感じるため、概算から減ったとしてもそれなりの量が増分として残るのではと期待します。
今すぐ、何も知らず、5分間この曲を聴いてほしい。32歳男性が音楽をやめて選んだ道。ラストに訪れる衝撃
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
ネタバレのため改行入れました。
私の母は、2005年度入試で”合格者の平均点”を10点以上上回りながらも、群馬大学医学部を不合格となりました。模試等でも十分な成績を取り、三回受験し、不合格を続け、初めて成績の開示を求めたところ判明したのが、この点数でした。
2018年に騒動になった医学部入試不正の際、文科省に当時の真相調査を依頼しましたが、個別案件には関わらないとのことで、梨の礫で対応いただけませんでした。
結局、同じような砂を噛むような思いをする人がまだこの国にいるという事実に愕然とします。どうしたら文科省は抜本改革に動いてくれるでしょうか。
米、月面探査の参加国に協定要求 平和目的を確認、衝突回避も
佐藤 将史一般社団法人SPACETIDE 共同設立者・COO/理事
先だってのロイターの報道では日本は米国がlike-minded countryとするtier 1の国になり、米国からのコンタクトがあるはずで、日本の外務省の回答が待たれます。
今回の協定、ざっと見たところ自分の理解は下記の通り。
•1967年(!)の国際宇宙条約に準じたものであることを強調→その実は「古い物を書き換える」ためのものでしょう
•天体の環境と安全を保全する平和利用を大目的としつつ、その実、一番入れたいのは“民間企業を交えた資源開発の推進”→建前と本音を使い分けながら、新しいルールが作られるのだと思います
•主な二国間の取り決め項目は、
緊急時の宇宙飛行士の援助、
月面で活動する宇宙物体の事前登録ルール、
月面の科学データのオープンフリー化の推進、
月面の歴史遺産の保護、
月面資源の採掘と利用の推進
月面における安全区域の制定と公表
月周回軌道のデブリと宇宙機廃棄のコントロール
宇宙ビジネス目線では、
・データのオープンフリー
・宇宙資源
・安全区域の制定
については、かなり気になる所。
国家主導でルールを決めたり無償の政府アセットが出回るのは、市場の信用に繋がり投資を促す一方で、企業活動を毀損することにもなり得るため、さじ加減が極めて絶妙でないといけないです。
4月に出た日本の宇宙基本計画(案)は、数年に一度の大改訂となりますが、月面探査における民間活動については、参入を促すといった程度の抽象的な記述に留まり、今回のArtemis Accordsのように、民間参入を見据えた具体的な枠組み検討からはまだまだ程遠い印象を受けます。
米国からのプレッシャーによって日本政府がどう月面と向き合うのか、政策的な分水嶺に来たと捉えています。

NORMAL

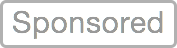











投稿したコメント