ホーム
117フォロー
703フォロワー


神奈川の中学2年生「10人に1人が貧困家庭」 県が初調査、支援ニーズ把握へ
加藤 陽子
貧困には絶対的貧困と相対的貧困がありますが、記事は相対的貧困を指していますね。
2つの違いについては、下記リンクがわかりやすく説明しています。
【相対的貧困とは?絶対的貧困との違いや相対的貧困率についても学ぼう】
https://www.worldvision.jp/children/poverty_18.html#d0e9d87eb78fa54e47cd213ca7606442
以下、リンク記事から引用です。
相対的貧困とは、その国や地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態のことを指しています。所得でみると、世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分(貧困線)に満たない状態のこと。
絶対的貧困とは、国・地域の生活レベルとは無関係に、生きるうえで必要最低限の生活水準が満たされていない状態のこと。
貧困は事象に過ぎず、それに伴う課題把握と対策が重要です。
こども自身の力ではどうしようもできない状況に対して、どのような形でどこまで社会(公的機関)が担うのか注視したい。
子育てと介護重なる「ダブルケア」29万人 9割が働く世代
加藤 陽子
日本は、年々生産年齢人口は減少していますが、高齢者は2042年まで増え続けることは、ほぼ確定しています。
これを踏まえてマクロの視点で考えた時、施設入所は介護保険財源負担が在宅より圧倒的に大きいため、高齢者は『できる限り在宅生活を』の方向性は合理的。
そして、在宅介護をミクロで実行するために、直接的な介護に関しては『家族が担うもの』という常識を『近隣の高齢者同士で担うもの』に変えられると良いのではないかなぁと妄想しています。
介護を要する人は、高齢者の2割程度。
であるならば、元気高齢者が複数の要介護高齢者をサポートしながら多様な終末期を観察し、その過程で自身の終末期を考えたり介護する側の気持ちを理解したりできれば、自身が要介護状態になった時に、介護者を不快にしたり過度な要求を突きつけたりする可能性は減るし、介護サービス知識もつくため自分の希望する介護を受けやすくなるなど、良い循環が生まれる気がしています。
また、年々増えている孤独死した場合でも、ご近所さんが頻回に顔を出す環境ができていれば、ご遺体の早期発見につながる可能性が高くなり、賃貸生活の場合は大家さんのリスク軽減になります。
ほか、生産年齢世代からみても高齢者間での介護を行えば税負担も抑制できるため、世代間対立やら不満は軽減されるかもしれません。
世帯員数が縮小している日本。
だからこそ、これからの介護は『家族でなんとかしよう』というのではなく、『地域でなんとかしよう』に切り替えないと、これから爆発的に増える高齢者に対応することは、極めて難しいと感じています。
進んで家族での介護を希望する介護者を否定するものではありませんが、過渡期を転換期にするチャンスとして2025年を捉え対策を考えたいものです。

NORMAL

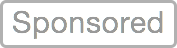











投稿したコメント