ホーム
29フォロー
2081フォロワー



【徹底分析】SaaS業界「冬の時代」はいつまで続くのか?
野口 竜司株式会社ELYZA 取締役 CMO
AIの専門家の視点からとなりますが、
「各社のSaaSプロダクトは最新AIで顧客提供価値が大化けする」可能性がまだまだ残っていると思います。
これまでの主流なSaaSは、既存のアナログ(もしくは都度手間がかかるような)業務をデジタル化やクラウド化することで便益をえるものが多いのではと思う。
デジタル化・クラウド化することで、得られるデータも生まれてきているはずだが、このデータを活かしきれているのか?にフォーカスして深掘りすると、プロダクトのバリューアップにつながる議論ができるかもしれない。
最新のAIは数年前は不可能とされていた、言語を理解し「書く、読む、話す」ものになっている。これらの知能を各SaaSにバンドルするとどうなるか?
発想がとまらないほどワクワクするテーマだと思います。
そしてSaaSの時価総額評価の考え方にも影響するような変化を生み出す鍵が、最新AIのSaaSへのバンドルかもしれない。

【独占】富士通が、ひそかに新会社を設立していた
1と0は遠くて、1と7は近い——AIは手書きの数字をどう認識している? “AIの頭の中”にある多次元データをのぞこう!
野口 竜司株式会社ELYZA 取締役 CMO
AIを理解し活用する際に、いわゆるAIの「手触り感」を得るというのはとても大事なポイントとなる。画像を取り扱う識別系AIや単語や言葉の距離やベクトルで扱う会話系AIについて、中身を垣間見る上でこの記事はとても有効だと思います。
一方で、ファウンデーションモデル(基礎モデル)と言われるような大規模モデルが脚光を浴びる中で、今回のような基礎を知りながらも、大規模モデルの構造の理解を同時に促してあげたほうが、現代のAIの立ち位置についても正しく伝えることができるだと思う。
その上では、今回の紹介している手法が既にとてもクラシックなものであることをもれなく読者に伝えてあげるとミスリードもなくよりベターな気がいたしました。(この記事が有効であることは変わらずですが)
その求職者は実在する? FBIが“ディープフェイク”を悪用したオンライン採用面接に警告
野口 竜司株式会社ELYZA 取締役 CMO
この記事をざっくり言うと
・米連邦捜査局が「ディープフェイク」を悪用したオンライン採用面接に警告
・FBIによると、求職者が面接中にせきやくしゃみをした際に違和感を覚えたそう
・他人の個人情報を提出していることも判明
ディープフェイクで逮捕者がでる。これはAI時代の常識として広く教育したほうが良い。悪気なく?技術を活用して、罪を負う人がでるのを防いだほうが良いし、情報を受け取る側においてもウィルス検知ソフトならぬ「フェイク検知ソフト」を各ローカルディバイス側に搭載した方が良いのかもしれない。プラットフォーマー側にもフェイク検知の搭載や強化が進むだろうが、最終的には各個人での防御力をあげておく必要はあるだろう。
IBM、「世界のAI導入状況 2022年」を発表 AI導入率は昨年比で着実に増加傾向
野口 竜司株式会社ELYZA 取締役 CMO
この記事をざっくり言うと
・IBMは「世界のAI導入状況 2022年」の日本語版を発表
・AIの導入率は前年の2021年と比較して着実に高まっている
・AIがより利用しやすく、実装しやすくなってきていることが浮き彫りになっている
企業におけるAI導入が進むない理由のひとつに「専門家の不足」があるという。この専門家ってどんな人なのか?をもっと解像度高く定義することがまず必要なのだろう。「データサイエンティスト」「データエンジニア」といったAIを作る側の専門家だけの定義では足りない。「AIプロデューサー」「AIディレクター」といったAIプロジェクト推進者や、学習データを集める「AIアノテーター」の明確の定義がそろそろ国内でもあって然るべきだろう。
また、専門家以外の一般職も「AI企画や利用が十分にできる」という認定やレベル定義が生まれ浸透すると、AIの導入率やそれによる成功率が上がるのではないだろうか。
レビュースコアの「アルゴリズム」はなぜ非公開なのか?

NORMAL

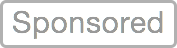











投稿したコメント