ホーム
2336フォロー
17422フォロワー


テスラ車大量発注が誤算-米レンタカー大手、EV過信で大変革に失敗
大場 紀章エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表
車利用率の高いレンタカー事業で走行距離あたりのコストが低いEVを使うというアイディア自体はよかったが、レンタカー事業は値段が落ちにくい車を中古車市場に再販する自動車ブローカーとしての大きなリスクを負っているので、特定の車種に賭けてその価値が下がってしまったらどうしようもない。
また、旅行者は不慣れな土地を走るので、いくら燃費がよくても充電リスクの高いEVは好まない。
EVの再販価格が大きく下落せず、一般ユーザーがEV利用に慣れている、という時代が来た上で、走行距離あたりのコストの安さで旅行者にメリットをうち出せるようにならなければこの事業モデルは成立しない。
結局、EV=テスラの時代に高値掴みしただけとも言え、参入が早過ぎた、タイミングが悪かったと言えるだろう。ただ、いつかはEVが個人所有車よりもレンタカーに向く時代というのが来るのではないだろうか。
燃料にミドリムシは入っていない バイオベンチャーの雄「ユーグレナ」の現在地 新規事業でも巻き返せるか!?【経済記者インサイト】(2024年3月29日)
大場 紀章エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表
ユーグレナの問題、知ってる人は知っていた。巧みなマーケで乗り切って来たが、安倍さんが亡くなってバックが弱くなったのかメディアの扱いに変化か。
https://www.euglena.jp/news/n20150123/
Newspicksは最近はかつて推していたようなベンチャーの闇に切り込むことがしばしば(空飛ぶバイクのA.L.Iテクノロジーズなど)あるが、ユーグレナに対しては過去の付き合いからして無理だろうか。
https://newspicks.com/live-movie/2790/?utm_medium=urlshare&utm_source=newspicks&utm_campaign=np_urlshare&invoker=np_urlshare_uid145483
8億程度の価値しかない横浜の廃油精製プラントを60億で作ったがそれも閉鎖。
https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC029MX0S3A001C2000000
NEDOから恐らく20億以上の助成を受けてインドネシアにプラントを作る計画が、ちょっとしたバスタブみたいなもの作って終わり。
https://www.euglena.jp/news/20201005-2/
https://newswitch.jp/p/26633
マレーシアの投資計画も昨年末までに発表と言いながら何も音沙汰なし。
https://www.zaikai.jp/articles/detail/3157
一体数十億のお金をどこに使ったんですかね。
一方で、真面目に藻類事業に向き合って来た、世界最先端のちとせ研究所にもう少し日があたっても良いと思います。
そろそろ、本当のエネルギーの話をしよう
大場 紀章エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表
本当のエネルギー、、、。石油と車の話、なぜか私は呼ばれないんですね。あ、水素と合成燃料の話だからか。
5:06
「COP28で、10年間で化石燃料を脱却」
↓
実際には「10年間で化石燃料からの転換(transition)を加速」が合意されただけ。「脱却」は日本のメディアの誤訳。だいぶニュアンス違う。
6:42
「2035年までに新車販売で電気自動車、電動車を100%」
↓
「電動車」は日本の政策用語でハイブリッド車を含む概念。恐らく数秒モーター走行できる軽のハイブリッドも認められる。EVはごく一部になるでしょう。
10:26
「50万円のEV」
↓
上汽通用五菱汽車の「宏光MINI」のことだろうが、流行ったのは2,3年前のことで今は殆ど売れてない。今更話題にするのもどうかと。
12:26
「充電スポットが増えないと使いたいと思う人は増えない、使ってる人が増えないと充電スポットは増えない」「結局ジレンマ」
↓
これはジレンマではなく、ビジネスは常に需要プルなので、充電スポットが先はない。多少不便でも使いたい人/使わせたい人が増える様な商品でなければ永遠に普及しない。
17:44
「海は全部水素だと思っても良い」
↓
身近なものは炭素を含む物質だらけなのにわざわざ中東から石油輸入している。物質がある事とエネルギーとして使える事は全く意味が違う。
26:37
「CO2が増えない自動車を作ることができる」
↓
合成燃料は炭化水素なので燃やせばCO2はでる。空気からCO2取ればプラマイゼロだが、それだと高くつくので、排出されているCO2から使う事になる。合成燃料の合成に使われた再エネの分だけ排出削減に貢献できるが、変換効率が悪すぎて、その再エネを電力として使った場合よりは排出量が増えてしまう。
28:22
「非常に大きな力が必要な車はEV化が難しい」
↓
コマツの930Eなど超大型になると低速でトルクの強い電動の方が有利になる。トラック等でもバッテリーは大きくなるが、その分エンジンが不要でトータルのシステムの大きさはさほど変わらない。バッテリーの価格次第。
29:01
「水素で燃料電池車を動かしたり」
↓
22:34頃に水素をMCHにして運ぶ話があるが、この方法だと生成した水素にヘキサンが残るので燃料電池用途には使えない。
1ビットLLMの衝撃! 70Bで8.9倍高速 全ての推論を加算のみで!GPU不要になる可能性も
大場 紀章エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表
今最もホットな話題の1ビットLLM(正確には1, 0, -1の3つの値のみを使うのでlog[2](3)=1.58 bit)生成系のAIでは学習コストよりも推論コストの方がビジネス上重要なので、メモリや消費電力の節約が重要になる。
LLMの推論計算の大半を占めていた16ビット浮動小数点の行列演算(無数の加算と乗算)を、整数の加算のみに変換することで、モデルサイズが大きくなると(30億以上)メモリ使用量を減らして高速化できるなどメリットが出てくる。
エネルギー消費量はモデルサイズがある程度小さくてもメリットがでるようで、7nm チップ上の演算エネルギー従来モデル(LLaMA LLM)と比べ71.4分の1。End-to-Endでも、モデルサイズ1.3Bで18.6倍効率的、70Bで41.2倍効率的という結果。
食用コオロギ手がけるクリケットファーム、破産手続き開始決定 負債額は関連2社と合計で2億4290万円
大場 紀章エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表
先日のグリラス社のコオロギ研究所が営業1年足らずで閉鎖したのに続き、21年創業のクリケットファーム社も破綻。22年には1400平米の新工場を建設し、年間1600万匹の生産が可能と言っていました。
見学できるスマート工場を標榜していましたが、QRコードで管理、ロボット2台投入で給水給餌と、この規模のコオロギ生産設備では殆ど意味がないIT化
で、うまくいかないだろうなと思っていました。
この会社場元々はブロックチェーン事業を手掛けるINDETAIL社が母体ですが、ITからコオロギをやって失敗するパターンはよくある話です。本業の方も業績悪化していたようですね。
食用というと注目されて資金調達しやすいのですが、事業性はペット用の方が圧倒的という罠があります。話題性で集金して代替物のある領域に無意味参入するやり方は、ブロックチェーン業界と構造が似ています。
諏訪信用金庫、および、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)長野支店農林水産事業より4,100万円の協調融資、クラウドファンディング「FUNDINNO(ファンディーノ)」のプロジェクトで、目標額800万円を大きく上回る上限応募額の3200万円を調達。ただ、キャンプファイアでは50万円目標で2万7000円しか集まってませんでした。また、長野県茅野市から認定農業者として助成も受けていたようですね。長野県立大学とも共同研究。お疲れ様でした。
寒暖サンタさんの試算で1平米で年間5キロ程度と言うことですが、私のファームならその10数倍は取れてました。

NORMAL

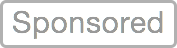











投稿したコメント