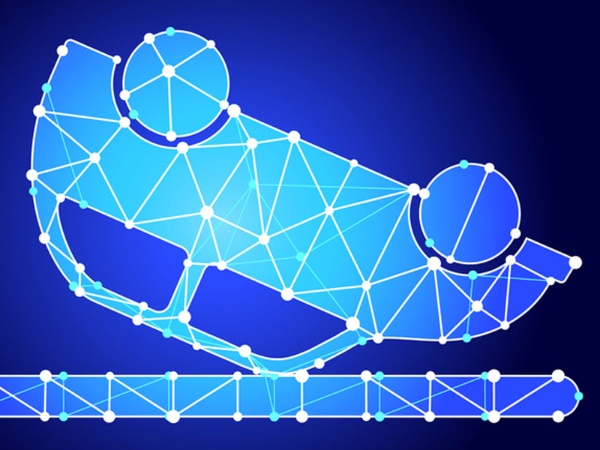日本人は欧米人とは違い、新築住宅が大好きだとよく言われる。「古い建物を大事にせず、スクラップ&ビルドを繰り返している、もうそんなことはそろそろやめてはどうか」という意見はよく聞かれる。また、「日本の住宅寿命は30年程度で諸外国よりも著しく短い」という指摘もある。しかし、データからは、そのような“新築信仰”は近年、薄れてきたことが読み取れる。なぜ新築信仰が薄れてきたのか、そもそも新築信仰とは何だったのかを考えてみたい。

日本人の新築好きの根拠の1つとして日本の住宅寿命が短い、ということが指摘されている。この「日本の住宅寿命は30年程度」という説は、いつ、どこから出てきたのだろうか。筆者が確認した限りでは、公的な調査での初出は恐らく1996年の建設白書だ。そこには「日本の住宅の寿命は、建築時期別のストック統計から試算してみると、過去5年間に除却されたものの平均で約26年、現存住宅の『平均年齢』は約16年と推測される」と記載されている。
ここで指摘したいのは、この建設白書の記述はあくまでも過去5年に除却された住宅の平均築年数が約26年だったというだけで、日本の住宅全体の寿命をきちんと把握した数値ではないということだ。住宅寿命の測定方法にはいくつかの手法があるが、ここではサイクル年数を見てみよう。サイクル年数とは、住宅ストックの総数を年間の新築着工数で割った値であり、今のペースで建て替えを続けると何年で全ストックが建て替わるか、という数値である。
「住宅・土地統計調査」のデータを暦年に平準化して、住宅着工統計のデータと組み合わせて計算できる過去のサイクル年数は以下のようになっている。
- 1950年:54.3年(住宅総数1471万/着工数27.1万戸。以下同じ)
- 1960年:42.4年(1919万/45.3万)
- 1970年:18.6年(2778万/149.1万)
- 1980年:30.2年(3671万/121.4万)
- 1990年:26.2年(4356万/166.5万)
- 2000年:42.6年(5170万/121.3万)
- 2010年:71.8年(5880万/81.9万)
- 2018年:65.5年(6241万/95.3万)
これを見ると、サイクル年数は1950年から1970年まで減少傾向にあったが、1980年代に入ると再び延びる傾向にあることが分かる。これの意味するところは何か。1960年ごろまでは、日本はまだ戦後復興の過程にあり、必要な住宅すべてを新築できるほどの余力がなかったため、サイクル年数が40年以上と長かったと考えられる。その後、高度成長期に入ると住宅着工は急増し、サイクル年数が短くなっていった。ちなみに最も短かったのは1972年の16.1年である。
オイルショックで高度成長が終わるとサイクル年数は少し延びるが、1996年までは30年程度で推移してきた。しかし1997年以降、サイクル年数は延び続け、現在では60年を超えるようになっている。くしくも、「日本の住宅寿命30年説」の初出と思われる建設白書が発行された1996年から、日本の住宅寿命は約30年を超えて急激に長期化し始めたことになる。
なお、サイクル年数以外にも、建物寿命の研究は行われており、早稲田大学理工学術院名誉教授の小松幸夫氏らの研究では、新築された建物が50%残存率になる年数を平均寿命として推計が行われている。2014年3月に発表された国土交通省「中古戸建て住宅に係わる建物評価の改善に向けた指針」の参考資料に記載されている研究成果を見ると、1997年時点でも木造専用住宅の平均寿命は約44年で、2011年には約65年と大きく延びている。これはサイクル年数の傾向と一致している。また、新築着工自体も高度成長期には建て替えよりも純粋な新設のほうが多かったが、近年では新築着工に占める建て替えの比率が上昇している。それを裏付けるように、住宅ストックの純増数は新築着工数よりも大幅に少ない。
「旧耐震」と「新耐震」で大きく変わった
さて、こうした新築着工数の減少と住宅寿命の長期化は、何が原因なのだろうか。経済情勢を見れば、バブルが崩壊し、デフレが進んだ時期と重なる。新築住宅を買う経済的な余裕がなくなり、中古住宅で我慢するようになったという面はあるだろう。しかし不動産に長年関わってきた実体験からすると、そのような消極的な理由だけでなく、積極的に中古住宅が選ばれるようになった点を指摘したい。キーワードは「旧耐震」と「新耐震」である。
「新耐震」とは、1981年の建築基準法改正により定められた新たな耐震基準のこと。1978年の宮城県沖地震を受け、大きな見直しが図られた。新しい基準に対応した住宅は、通称「新耐震」と呼ばれ、それ以前の建物は「旧耐震」として区別され急速に市場での商品価値を失っていった。実際に昔の戸建て住宅を見てみるとよく分かるが、旧耐震の建物は現在の水準からみればとても快適に住めるようなレベルの品質ではない。1981年の建築基準法改正を契機として、急激に住宅品質が向上していくことになったのである。
中古住宅市場に出る物件の築年数はさまざまだが、木造住宅の法定耐用年数が22年なので、ここでは築年数20年を基準に考えてみよう。1980年当時なら1960年に建築された建物、1990年当時なら1970年に建築された建物、すなわち旧耐震である。ところが2001年を過ぎると、1981年以降の新耐震に該当するようになった。
ここで強調したいのは、新築物件と築20年の物件の差は、老朽化ではなく陳腐化である、ということだ。1960年代といえども、20年程度で建物自体が老朽化するほど低品質な建物を建てていたわけではない。1981年の新耐震により住宅品質が急激に向上していくことで、陳腐化が起きていた。だから新築が選ばれるケースが多かったのだ。
もちろん、建築技術は常に進歩している。ただ、1995年の阪神大震災の被害を検証してできた新・新耐震(2000年基準ともいう)は1981年の新耐震の時ほど、基準が大きく変わったわけではない。また、水回りやエアコン、サッシなどの住宅設備の著しい性能向上も2000年くらいまでで、その後はあまり大きな変化がない。陳腐化のペースが衰えた結果、中古住宅を選ぶ人が増え、住宅寿命が延びていると考えられる。
陳腐化という視点では、日本人のライフスタイルの変化も大きく影響していよう。1つは、畳に座る生活から椅子に腰かける生活への変化であり、2つ目がエアコンを前提とした生活への変化である。
間取りの変化とエアコンの普及
畳から椅子への変化は、間取りの変化として典型的に理解することができる。イメージとしては、和室が田の字型に並んだ「サザエさん」の磯野家の間取りと、洋室だけで和室がない「妖怪ウォッチ」の天野家の間取りの違いである。ちなみに「クレヨンしんちゃん」の野原家はその中間で、洋室の中に和室が1つだけある。
こうした間取りの変化についての考察は、小松克枝・高橋英樹のリポート(2017)「人口減少を『住まい方の質』を向上させる好機と捉えるまちづくり政策について」(都市住宅学)を参照いただきたいが、1980年代であっても、磯野家のような間取りの家は、市場での競争力を失っていたことは容易に想像できる。そして、和室がほぼなくなった間取りが様式として確立したのが1990年代なのである。
もう1つの大きな生活様式の変化としてのエアコンの普及は、建物構造やサッシなどに大きな影響を及ぼした。もともと日本の家屋は、約700年前の「徒然草」で兼好法師が「家のつくりやうは、夏をむねとすべし」と述べているように、気密性や断熱性を全く考慮していないのが普通だった。それが1970年代からエアコンが普及し始め、1990年代には当たり前の生活になっていった。
この変化に日本の旧来の住宅は構造的に適応できなかったことも新築着工を後押しした側面がある。このエアコンに対する建物構造は、欧米と気候風土と国の成り立ちが大きく違うことも関係している。北米を含め欧州各国の冬の気候は厳しく住宅そのものが冬を基準につくられている。そのため欧米では100年以上前から、断熱性や気密性を考慮した住宅が建設され、それがそのまま現在も使われている。そして、産業革命や植民地の存在などによって国力が早くから蓄積され、建築物・都市への投資余力があったことも大きい。そうした歴史的背景の違いを無視して、日本の住宅寿命の短さを批判することはフェアではないだろう。
このように、住宅技術の急速な進歩や日本人のライフスタイルの変化がもたらした陳腐化が、「20年で建物は無価値になる」と言われてきた主要な理由なのだ。中古住宅が築20年を超えても比較的陳腐化しなくなっている今では、「注文戸建て住宅のような特別のこだわりが無ければ、中古住宅も充分に選択肢に加えてもよい」ということになる。
今回は、主に住宅の技術的な側面から、“新築信仰”が薄れている理由を考察してみた。しかし「それでも諸外国に比べて中古住宅が流通していないではないか」という意見もあるだろう。次回は住宅流通の視点から、新築と中古の違いを考えてみたい。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「データで解き明かす不動産の真実」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。