リクルートが次々と新たな事業を生み出し、それを大きく成長させることができるのはなぜか。経営コンサルタントという立場から17年にわたってリクルートを見てきた、ボストンコンサルティンググループ日本代表の杉田浩章氏は新著『リクルートのすごい構“創”力』の中で、それは天才たちのひらめきではなく、確固とした仕組みやフレームワークによって作り上げられたものだと語っている。リクルートワークス研究所副所長の中尾隆一郎氏との対談から、新規事業を生み出し続ける「リクルートの構“創”力」の実際に迫った。
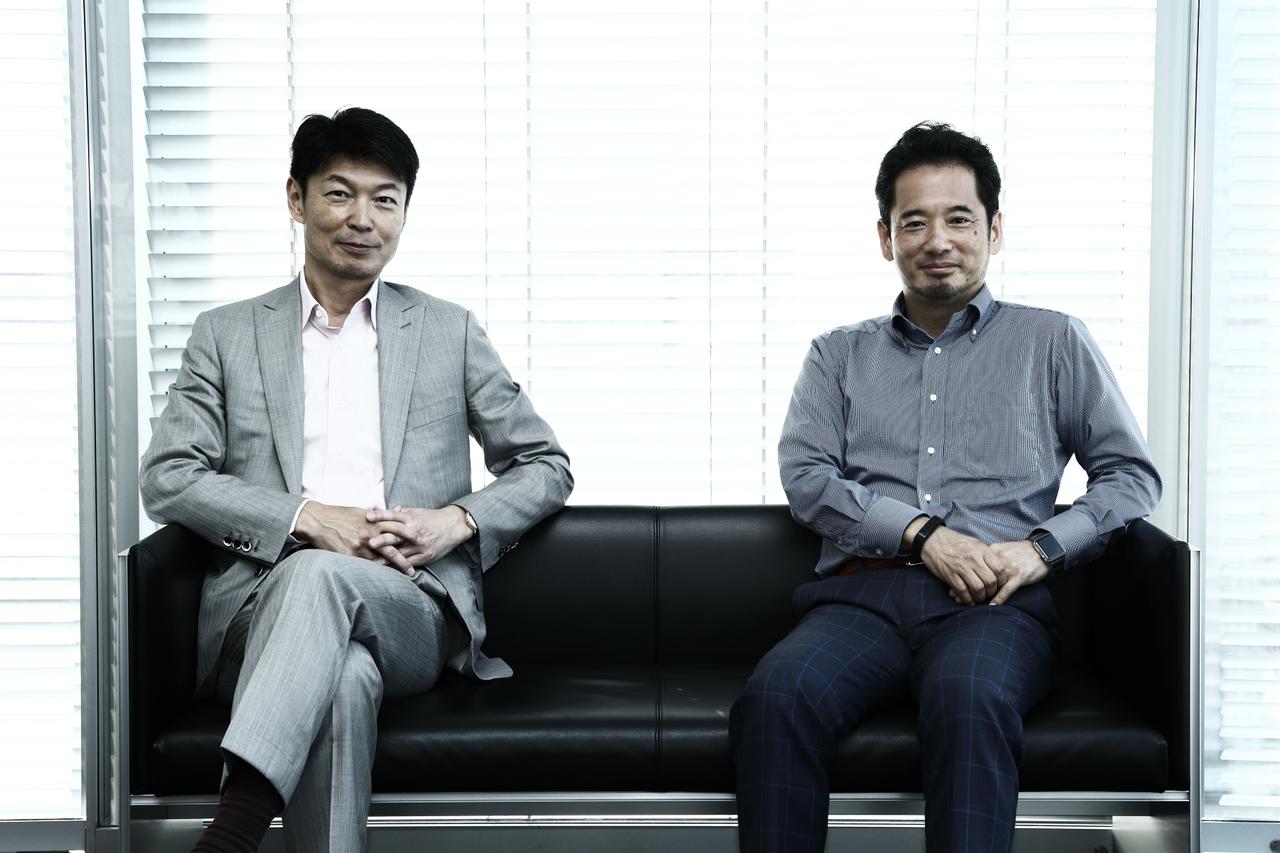
リクルートはなぜ次々と新規事業を生み出せるのか。ボストンコンサルティンググループ日本代表の杉田浩章氏(左)とリクルートワークス研究所副所長の中尾隆一郎氏が語った。
日常会話に常に出てくる「リボンモデル」
Business Insider Japan(以下BI):杉田さんとリクルートとの関わりはどのようにして始まったのですか?
杉田:最初に一緒にお仕事をさせてもらったのは、2001年のことです。当時はまだ紙の時代で、それをどうネット化していくかを議論している時期でした。まだ「本当に広告がネットになるのか?」「なったとしても単価が何十分の一になるのでは事業として成り立つはずがない」という声が多く、会社としても二の足を踏んでいたんです。でも、当時の経営企画の人たちは、ネット化を進めることの必要性を経営陣に訴えたいと考えていた。そこでいくつかの事業領域におけるネット化進展の事例を提示し、それをサポートするというところから、お付き合いが始まりました。
BI:中尾さんとの出会いは?
中尾:その後、リクルートがカンパニー制を敷き、私はそれぞれのカンパニーを監査する立場になりました。就任するにあたって1日研修があったのですが、そこで講師をやっていたのが杉田さんです。
BI:杉田さんは著書の中で、「リボンモデル」「RING」「ぐるぐる図」など、リクルートが次々と新規事業を生み出せる背景には、いくつもの独自の仕組みやフレームワークがあると語っています。こうしたものは、お二人が出会った当時からすでにあったのですか?
中尾:RINGに関しては当時からありました。
杉田:1981年に創設されたRINGは、日常業務の改善活動について成果発表をする会として始まり、1990年代に入って、新規事業の創出に特化したNew RINGへとリニューアルされたと聞いています。新しいものを生み出すという風土そのものを作ることに重きが置かれていた時代もあれば、実際に多くのアイデアが持ち上がるようモチベートすることが重要視された時代もあり、その後も何回か刷新されていますが、変わったのはどこに力点を置くかという点であって、新規事業を作るという目的自体は一貫していると認識しています。
景気の変動にとらわれずこだわった新規事業

BI:今でこそいろいろな会社で新規事業を生み出すための仕組みづくりをやっていますが、当時からやっていたのは珍しいのでは?
中尾:そんなことはないでしょう。例えばメーカーさんには、新規事業提案などの小集団行動をしているところが、当時からたくさんあったと思います。我々にユニークなところがあったとすれば、景気の変動にとらわれることなく、それをずっとやり続けたことでしょう。インセンティブをつけたり、新規事業のためなら社外の人も巻き込んでいいというルールを作ったりと、当時からずっと役員が妙にこだわりを見せていた印象があります。
BI:そうやってできた仕組みが、形は変えつつも現在まで続いているんですね。せっかく作った仕組みや機運も、一過性に終わって長続きしない組織が多い気がします。
中尾:おそらく、リクルートはどこの会社よりもしつこい。諦めない。だから、新規事業を生むRINGにしても、産業構造全体を俯瞰してビジネスモデルを構築するリボンモデルにしても、1回作ったらそれを改良しつつ、ずっと使い続けようとするのです。
杉田:なおかつ、単なる概念としてあるのではなく、それを一人一人が日常的に使い続けているというのが強いのだと思います。中尾さんもそうだと思うんですが、リクルートの人というのはみんな、何か議論をしているとすぐにリボン図を書くんです。

リボンモデル
出典:『リクルートのすごい構“創”力』
中尾:確かにそうですね。「今の話はリボン図でいうと、カスタマー側の話をしているのか、それともクライアント側の話をしているのか」とか、「集めるフェーズなのか、動かすフェーズなのか、結ぶフェーズなのか」とか、日常的な会話の中で地図のようにして使っていますね。
杉田:そう。そうした中で、OJT的に一人一人に染み付いていったという部分が大きいのだと思います。
核心を突く質問をする上司が圧倒的に多い
BI:リクルートに新しいものを生み出そうという風土があるのは、やはり創業者である江副浩正さんの精神によるところが大きいですか?
中尾:そうだと思います。例えば、小集団で活動して、そこでいくらかでも収益を出したら、それを自分たちの次の活動に回していいという「プロフィットセンター」の考え方などは昔からありました。何か新しいものを生み出さなければという、強迫観念のようなものは確かに社員の中にあるかもしれませんね。
BI:それは教えられて身につくものですか? それとも初めからそういうDNAを持った人を採用しているのですか?
中尾:リクルートという会社の中で過ごしていると、一時的には業績がよかった事業も、それを改良できなかったり、次のサービス展開を生めなかったりすれば衰退していくということを、日常的に目の当たりにすることになります。教えられたというより、そういう環境に身を置いていることで、自然と身につけていっているのではないでしょうか。

杉田:その点に関して第三者から見て感じるのは、一つには、リクルートは個をとても尊重する組織だということです。年次や経験に関係なく、各人が持っている発想をすごく大切にする。新入社員だから3年、5年下積みしろというのではなく、入社した直後から「お前は何がしたいんだ?」ということを突き詰めて問うわけです。おそらくその背景には、若い人には新しい何かを生む力があると信じているところがあるのでしょうが、そのことが、社員一人一人から新しいアイデアが出てくる風土を育んでいるように思います。
そしてもう一つ、リクルートが他の組織と決定的に違うのは、核心を突くいい質問をする上司が非常に多いことです。
BI:いい質問、ですか。
杉田:新しいビジネスのアイデアを提案してきたメンバーに対し、「こういう結論を出したのはなぜなのか?」「このビジネスモデルを採用した場合、それって誰が嬉しいの?」など、厳しい質問を投げかけ続けるのです。その上司の質問能力が、他の会社のマネジャーと比べて圧倒的に高い。一般的な企業では、新規事業であるのにもかかわらず、「数字がどれだけ上がるのか?」「どれくらい儲かるのか?」といった質問ばかり出てくることが多い。質問のポイントが分かっていないんですよね。
中尾:事業として成立させるまでにクリアしなければならないポイントが5つあるとしたら、リクルートではそのポイントを突いた5つの質問が、順を追って投げかけられます。つまり、質問が事業化のためのファシリテーションの役割を果たしているということです。ここでは、検証すべきポイントだけでなく、最適な検証の方法や、それを選んだ理由まで細かく質問されます。それに対して、確たる根拠もなく頭の中の妄想だけで答えると、ものすごく怒られることになります。
BI:リクルートにはなぜ、それができる上司がそろっているのでしょうか?
杉田:やはり、会社として新規事業をたくさんやっていることが大きいのだろうと思います。新規事業に直接間接に触れる機会が多いから、その過程を通して、新規事業を作る上で何が大切なのかというのがOJT的に叩き込まれていく。さらに、そうやって学んだ人の中から、特にそれが得意な人だけが上へ上がることになりますから、それでまた拡大再生産されていく、ということが言えると思います。
フェーズにより躊躇なくトップを入れ替えられる
杉田:リクルートと他の組織の違いとしてもう一つ重要なのは、リクルートは事業のフェーズによって、トップを入れ替えるということをドラスティックに行えるということです。例えば中尾さんの場合で言えば、住宅領域の新規事業であるスーモカウンターを担当し、6年間で売り上げ、店舗数、従業員数を急激に成長させ、同時に生産性の向上も実現しました。でも、この事業を最初に立ち上げたのは中尾さんではありません。
前任者は0→1のフェーズにいたので、自分なりのアイデアをどうすれば需要につなげられるかということにフォーカスしてやっていました。ただ、事業として成功するためには、今度はそれをどうにかして収益を出せるモデルにしていかないといけません。そこで、収益化をどう実現するかを考えるタイミングで、その点について長けている中尾さんが引き継ぐことになったのです。
この決断が、一般的な組織にはできない。立ち上げた人に悪いからという理由で、このような入れ替えをためらってしまうのです。でも、新規事業を立ち上げ、大きくしていく上では、各フェーズごとに必要とされる能力は違いますし、各人が持っている能力もそれぞれ違います。これらをうまくマッチングするためであれば、ためらわずに人を入れ替えることができるのが、リクルートという会社なのです。

BI:著書の中で、杉田さんは新規事業立ち上げのプロセスを、「0→1」「1→10の前半」「1→10の後半」の3つに分類して説明しています。中尾さんから見ても、各フェーズを得意とする人は、それぞれタイプが違うと感じますか?
中尾:明らかに違いますね。例えばリクルートワークス研究所長の大久保(幸夫氏)は、自他ともに認める0→1の人です。ドミノ倒しの最初の1枚を倒すこことにもっとも興味があると公言しています。彼がすごいのは、業界全体の構造を考えた時に、どこが大事なポイントで、そこに対してリクルートがどう貢献できるかという視点を常に持っている点です。もちろん、誰もがそういう視点を持って日々仕事をしているのですが、彼の場合はそのレベルが全然違うんです。
BI:中尾さんに代表されるような、1→10が得意な人というのはどういうタイプですか?
杉田:1→10と言ってもその前半だから、完成した部門をどう回すかというよりは、アイデアを事業に仕立てていくフェーズにあるわけです。そこでは組織を作り込む能力だったり、ビジネスモデルのさらなるイノベーションを起こす能力だったりが求められます。一方、1→10も後半になればよりオペレーティブになるので、メンバーをいかにモチベートするかということが重要になっていくと思います。
BI:配置換えのメリットは分かりました。ですが、多くの組織に配置換えの決断ができないのに、リクルートにそれができるのはなぜでしょうか?
中尾:事業会社各社の経営幹部の人事は、リクルートホールティングスの経営会議で議論して決めていました。今は3つのストラテジック・ビジネスユニットに分かれているので、それぞれのトップが同様の権限を持っています。いずれにしろ、組織のトップが百数十人全員の状況を完璧に把握しているということです。だからこそ、部分ではなく、全体最適で物事を見られるということがあるのだと思います。
杉田:普通の企業だったら、これからそのビジネスを広めていくという局面で担当者を変えるということはあり得ません。なぜなら、そのビジネスについて一番分かっているのは、立ち上げたその人に違いないからです。
しかし、本当に会社全体のことを考えるのであれば、こうすればうまくいくだろうというモデルがある程度確立していて、別の人間がやっても成立するという状況にあれば、そこは若い人に任せて経験を積ませ、元の担当者は次の役割に回した方がいい場合もある。結局、経営層がどれだけ大きな視点を持って会社全体を見れているかというのが、多くの企業とリクルートの最大の違いと言えるのではないでしょうか。
(撮影:渡部幸和)
杉田浩章(すぎた・ひろあき):ボストン コンサルティング グループ日本代表。慶応義塾大学経営学修士(MBA)。日本交通公社(JTB)を経て、現職。トランスフォーメーション、グローバル戦略などのコンサルティングを数多く手がける。著書に『BCG流 戦略営業』。
中尾隆一郎(なかお・りゅういちろう):リクルートワークス研究所副所長。大阪大学大学院工学研究科修了。リクルート入社。リクルート住まいカンパニー執行役員(事業開発担当)、リクルートテクノロジーズ社長などを経て、現職。






