ホーム
8フォロー
19682フォロワー


胸にとめるAI秘書「Humane Ai Pin」発売。まだポンコツすぎる
土屋 武司東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
6年前のコメントですが,現実味を帯びてきました.
https://newspicks.com/news/2728789?ref=user_2112738
各個人に専用AIがアシスタント,秘書のようについてまわり,さりげなく行動や思考をサポートするようになるという世界が描けます.実態はどこにあるのか分かりません.ただ空気のように自分の事を分かっているAIが存在していて守護神のようにいつもそばにいる.人への出力(指示,アドバイス)は,BCI((Brain-Computer Interface)が実用化される前は,イヤホン(聴覚),メガネ(視覚)で行われる.一方,人にAIがつくように,モノにも専用AIがつく.例えば,自動車のように人を運んでくれる物体(乗り物,モビリティ).そこにも制御用のAIが存在しますが,人がそれに乗ると,人についているAIと乗り物についているAIが融合して,その人好みの行動をしてくれるようになるでしょう.お店にもAIがある.ある人がお店に入ると,その人のAI(好みを知っている)とお店のAIが交渉を始めて,買い物がスムーズにできる.AIがどこにでも自然にある,AI=空気 の時代が来るかなと.
埼玉に空港? 群馬県境市町で構想
ライドシェア解禁、「女性は絶対乗るな」ってほんと?
土屋 武司東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
このライドシェアは、利用者が運転手を評価する。また、運転手が利用者を評価する。そして、それを利用前に双方が見ることができる、という評価(レピュテーション)の仕組みが備わっているのでしょうか?運転手と利用者の質を中央が担保するだけの仕組みならば、それは不完全だと言わざるを得ません。運転手採用こそが利権ですから難しいでしょうね。
さらに言えば、その評価がライドシェアのサービス評価だけに留まらず(NewsPicksやSNSの書き込みも含め)、社会生活一般を送る上での信用度にリンクするくらいになって欲しいし、そうなるのではと思う。
例えば、ネガティブや癖のある書き込みをする人はライドシェアで車を捕まえにくくなるとか、運転手になれなかったり、なったとしても客が捕まらない、特定の客とマッチングしなかったり。
ダイモン氏、AIは最大の課題-蒸気機関に匹敵し得る変革を予想
土屋 武司東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
18世紀の産業革命の契機となった言われるワットの蒸気機関はワットが発明したのではない。ワットはそれまで経験的に存在した蒸気機関の効率を高めることに貢献した。このとき、governer(遠心調速機)と呼ぶ小さな装置を組み込んだ。このgovernerの役割は蒸気機関の出力を一定に保つ自動制御器である。蒸気機関が停止しないように、また暴走しないように、自動制御器を採用したことがワットの功績である。ちなみに、ワットはgovernerを発明していない。governerはそれ以前の動力機関である風車の中にあった。ワットはそこに目をつけたことこそが最大の功績である。
AIのgovernerはどこにあるのでしょう?
ちなみに、その後、蒸気機関が大型化・高出力化するにつれて、governerは思ったように機能しなくなり、蒸気機関が不安定になる現象が現れた。なぜ不安定になるのか?それを解明したのは、およそ一世紀後、電磁気学のマクスウェル方程式で有名なJ.C.マクスウェルである。彼が近代的な自動制御の歴史を開いたのである。
AIとそれを制御する歴史が始まる。

NORMAL

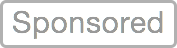











投稿したコメント