ホーム
54フォロー
4893フォロワー



セールスフォースが取締役追加、エリオット視野
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
新たに3名が新任され、2名が退任のアナウンスが出ていました。退任する2人は2003年から勤めていた方でそのうちの1人Sanfordさんは以前はMarc Benioffが来日する時はよく一緒に来てイベントなどにも見学に来られていた記憶があります。メディアの観測でもう1人リブレースのターゲットとされていた元Peoplesoft CEOのCraig Conwayは今回は残る方向のようです。
Peerの会社と比べて高すぎるSales & Marketing費用の比率や、Exeuctive層への高額なCompensationなどを考えるとActivist fundが手をつけるところはたくさんありそうですし、海外メディアではSlackやTableauを売却させる考えもあるという記事も出ていました。
しばらくの間、細かいものも含めて動向に関する記事が増えそうです。

【Notion】不景気の今こそ、「ノーコード」の波が来る
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
私自身は個人のメモや過去の資料類の整理などにNotionを活用しており、少人数でのナレッジ共有にも利用していますが、実際に企業で業務システムとして利用していくにはまだまだ壁が高いと思います。情報をどのように整理して残していくかについて個人であれば自分がやりやすいように設計すれば良いですが、企業で活用していくためには誰かがそれを設計して集中管理し、メンテナンスしなくてはならないので、その運用が非常に難しい気がします。昔で言えばフォルダの名称設定ルールなどと同じで利用する人数が多ければ多いほど運用フェーズで躓くのではと思います。Evernoteが個人利用では愛好者が多かったのに対してビジネスに振ろうとした途端に苦戦したのと被りますが、この記事にあるワークフローなどの方向性や複雑な権限設定など機能を拡充できればKintoneのように企業内システムで広がる可能性もあると思うので、今後のプロダクトロードマップには注目したいと思います。最後にこれはNotionについてではなく、一般的な話ですが業務生産性向上のツールについては、不景気の今こそ波が来るというより、「不景気の時代に真っ先にカットされやすい」カテゴリだと思います。「ノーコード」か否かよりも、そのツールによって行われている業務がどれくらい必要なものか。単に情報共有とか個人のタスク管理レベルのものなら、削減対象になってしまうので、どのような利用用途で使われているかが鍵になると思います。米国は12月決算の会社が多いので、解約等の影響は(10-12月期)に大きく影響が出ていますが、日本は3月決算の会社が多いので、来期の予算確保という意味ではこれから2月中旬くらいまでの動向は気になるところです。
セールスフォース、株価急落で幹部たちが続々と離脱
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
原題は「Salesforce Executives Have Millions Of Reasons To Leave Amid Share-Price Plunge」で、ニュアンスが異なります。この記事の趣旨は最後のゴードン氏のまとめにあります。“I doubt compensation is the only reason they're leaving,” Gordon told Forbes. “I think compensation plays a role, but there’s more to the story.」という箇所を「ゴードンは、フォーブスに次のように話した。「報酬も一役買っているが、他にも語るべきものはあると思う」と訳していて、日本語だけ読むとわかりづらいです。ポイントの一点目は株価や報酬も一部の理由だと思うが、それだけではないという点。買収した企業の経営陣が一定期間で退職するのは今に始まった事ではありませんし、この会社特有でもないと思いますが、Co-CEOに任命した人が続けて短期間で退職するのは何か理由があるのだと思います。私なりに仮説はありますが、この辺りをジャーナリストが掘り下げると面白い記事になるのではと思います。二点目のポイントはa super bull market over the last decade has made life easy for HR managers. They just had to dangle stock in front of recruits.という箇所です。一部の外資IT企業はこの10年近い上昇相場で一般社員にもRSUをばら撒きに近い状態で出す会社が目につきました。多くの場合4年に渡ってVestされて売却可能タイミングも明確。上昇相場であればマイナス面はありませんが、Vestされた時点で給与所得と見なされて所得税がかかる。その時点で売却せずに株価が下がっても損益通算はできないため、長く保有するとリスクが高い。またVestのタイミングで円安相場、売却時に円高でドルから日本円に戻したい時はリスクがあるので、今年は「こんなはずじゃなかった」という人も出始めているのではという気がします。いずれにしても本当の意味で採用力や自社の魅力を伝える力が求められてくるのは間違いないと思います。
セールスフォース、テイラー共同CEO退任へ-見通しも軟調で株下落
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
外から見た意見で実際はわかりませんが・・という前置きの上で、おそらく経営的に大きな変化はないのだろうと思います。この数年の状況を見ると、Keith Block, Brett Taylorをはじめ、後継者と思われた人たちが退職していく様子は90年代のOracleとよく似ています。両者ともカリスマ的なCEOですが、おそらくCEOになったとしても、自分が本当の意味でCEOとしての役割をさせてもらえるか疑問が出てくるのではないかと想像します。10年くらい前に当時の経営陣の中で誰が後継者になると考えているのかとMarc Benioffとの1:1で質問してみた事があります。その時の回答を思い出すと、Engineerではなく、営業部門などで数字責任を持っている人。但し、官僚的な人間ではなく、自分と同じアントレプレナーのマインドを持っている人を次のCEOとして考えていたように記憶しています。その点でBrett Taylorはアントレプレナーとしての要素を満たす人だったのだと思いますが。。カリスマ的なCEOがずっと経営を続ける事自体が悪というわけではありませんが、同じIT業界で見るとMicrosoftはいろいろありつつ、自社の主力製品を少しずつシフトさせて会社の体制も移行しつつ安定した成長を続けている点ですごい会社だなと思います。
ARR100億円のその先へ!海外SaaS企業のARR1000億円までの成長軌跡
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
2000年代にsalesforceの中では「過去に$1Bの売上を達成した企業は数少ない。この中でのどこよりも早く$1Bの売上を達成する」という事がマネジメントに向けてメッセージされていました。当時は$1Bなんて達成できるのだろうかと考えていた事を思うと、今や多くの企業が$1Bを通過点として見ているのはそれだけこのセクターが大きく成長している証拠だと思います。
海外企業の場合は、まず米国市場で基礎を築き、$30-50Mくらいで欧州を、$100M前後で日本を含むアジアパシフィックへ進出するという形で他地域へ売上基盤を広げていけるところが日本企業とは異なる点だと思います。これらの企業の地域毎の売上の割合を分析すると面白いかもしれないですね。米国市場に過度に依存しすぎている場合はどうしても成長が鈍化しますし、欧州・アジアでうまく立ち上げができれば高い成長率を維持できるという事になります。
記事中に出てくるSnowflakeは、上場前のタイミングで経営陣がシャッフルされる事態が起きて「これはあまり良くない事が起きているのか」と思っていたら、ServiceNowのCEOだったFrank Slootmanが着任して驚異的な成長を見せています。直接的な関わりはないのでPodcastや記事を見る限りの想像ですが、戦略としてSales Capacityを急速に拡大する。隣接した領域に製品を拡大していくマルチプロダクト戦略を採用している印象があります。ServiceNowでも大きな成長を遂げていますし、いずれも創業者ではないCEOとして成長させている点でこの人の手腕は大きいのではと想像します。同じく記事に出ているTwilioも2019年に当時のCOOが来日して食事した時に「創業者CEOは製品が良ければ売れるという考えで営業を採用したがらなかったが、自分が入社して営業を一気に拡大する事で成長した」と話していました。私は「単に営業を増やせば売れる」とは思いませんが、共通点としてはいずれの会社も1) 営業リソースの拡大 2)マルチプロダクトの展開 3) 米国外の市場への基盤作りの3つが揃っているのが共通項ではないかと思います。
国産SaaSのアメリカ展開はじめの一歩(3つのしくじり)
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
Japan Cloud関連の会社ではMiraklがフランス、WalkMeがイスラエルからスタートした会社ですが、いずれの会社も市場として最も大きいアメリカにも第2本社というべき規模のオフィスを設置しています。最近はCloud 100の中にもアメリカ以外の会社も増えていますので、これらの会社がどのくらいの規模でアメリカに進出しているのか。どのような組織にしているのか(R&DやCorporate機能を本社に残して、GTM機能の本社をアメリカにという会社が多い気がします)などを研究していくと、日本企業の海外進出のヒントになるかもしれないなと思いました。
人手不足の「大退職時代」が一変か テック企業が相次ぎ内定取り消しとレイオフ。米雇用市場の現状に迫る
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
先月米国出張に行ってきた時に、いろいろな人と会話した内容と概ね感覚は一致しています。
・業績が良い会社でも当面様子見をすべく、採用を一時見合わせるなど慎重姿勢を見せている。(本社の方針で日本にもその影響は出つつある。)
・(テクノロジー関連について)基本的には楽観的であり、今後も継続的な成長を続け人材不足(売り手市場)である事に変わりはない。
・この数年、売り手市場により賃金が高騰、特に若いエンジニアや営業が給与の高い会社を選択するため、経験値や能力に対して給与がアンバランスなまでに上昇した。
・ここ半年くらいレイオフをする時は、シニア層よりも若手で給与が高いが、パフォーマンスの出ていない層が対象となるだろう。
要は実力と給与のバランスが取れていない人が対象になるという事ですが、通常はシニア層が対象になりやすいものの、今回は若手にその対象者が多いというのはこの数年の給与高騰が背景にあると思います。
国内の外資ITでも「米国本社の給与水準に合わせて、自分達のオファー金額も上げるのは大歓迎」とばかりに、先のことを意識せずに給与を高騰させてきた会社や個人は少なからず影響を受けるのではと思います。給与が上がる事は良い事だと思いますが、その分自分が提供できる価値との比較がより厳しくなされる環境になると思います。
東京のコロナ警戒レベル「最も深刻」 3カ月ぶり、都会議決定
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
5月と6月に続けてアメリカに出張に行きましたが、数十人の人とミーティングしましたが、一度も感染してないという人がいなくて、自分が一度も感染してないというとものすごく驚かれたのが印象的でした。また非常に多くの人が複数回感染の経験があるようでした。"Mild Symptoms"という人がほとんどだったので、感染する事自体を大きなリスクと捉えていないのだろうと思います。
専門的知識がない事についてコメントはしないようにしているのですが、この件については一般人の感覚として、「マスクは効果がない・ある」も二点三点しますし、「ワクチンさえできれば」「ワクチンには数年かかる」「ワクチンが予想以上に早くできた」「ワクチン一回ではダメ」「ワクチンは感染を防ぐものではなく重症化を防ぐものである」「PCR検査は専門的知識が必要、コストがかかる」「突然街のあちこちにPCR検査場ができる」「偽陽性・偽陰性が一定数出る」「最近はあまりその点に触れられない」など以前に言われていた事が簡単にひっくり返される事が多すぎるのではないかと感じます。
「分業化した営業組織がうまく回らない」──SaaS企業の課題、セールスフォース流の解決策は
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
前置きとして、私が執筆した「THE MODEL」はこの手の記事で紹介されている「The Model」の図の説明ではありません。日本に導入する時に作成した原型のスライドは存在しますが、それはこれらのKPIを管理することが目的ではなく、個人の役割が明確に定義されていないためにどこに課題があるかわからない状態だったのを、役割の定義とそれに合わせた個人の評価制度を作るというコンセプトを説明するものでした。この記事でも数字を多面的に分析するアプローチについて紹介されていますが、例えば受注率が悪化した場合、その背景にはいくつもの原因が考えられます。件数ベースと金額ベースのどちらが悪化しているのか。大きな商談だけ失注しているのか、全般的に落ちているのか。特定の競合に負けているのか。以前は受注率が高かった営業も落ちているのか新規採用したメンバーの立ち上がりが遅いのか。どの商談フェーズで失注しているのか。マーケ、パートナー、営業など商談作成ソース別で差はあるのか。上司の指示で動いていない商談を一気に整理したために失注が増えたのではないか。商談を作れと指示されて、まだ柔らかいものも商談化したのではないかなど、受注率悪化一つを取っても想定されるシナリオはいくつもありますし、営業部門以外のところに問題があるケースも多々あります。原因を正しく特定しないと、間違った対策を打つ事になりますし、原因を正しく特定するためには、全体を俯瞰できる力、数字から何が起きているかを想像する力、人がどういう行動原理で動くかという事に対する理解が欠かせないと思っています。
企業の稼ぐ力を高める 確かなビジネスの未来予測とは
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
DevOps, MarOpsという言葉はこの数年広まりつつありますが、RevOpsという役割は重要度を増しています。営業系のツールというと商談管理や顧客管理を想像しますが、経営視点ではフォーキャストで少し未来の業績の予測確実性を高めて、どのセグメントやテリトリーにリソース配分をするのか。必要なキャパシティは。またそのリソースのパフォーマンスを最大化するための報酬設計をどうすべきかが重要となります。そしてこれらを統合的に管理できるのがXactlyです。企業の意思決定に直結する、CEO/CFOにとっても欠かせないツールとなるはずです。これから日本のお客様にもその重要性を広めていけたらと思います。
Gainsightが日本・APAC地域へ本格参入へ 世界トップのカスタマーサクセスプラットフォーム
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
Gainsight日本法人の立ち上げに関わる事になりました。この数年、日本でカスタマーサクセスに対する関心が一気に高まり、既に大きく取り組みに先行している会社もあれば、これからその考え方を吸収していこうという企業も多いと思います。私が長年、ソフトウェアベンダーで仕事をしてきて強く感じている事は、良いソフトウェアは実現したい世界観や理念が明確に存在し、ツールの活用を通じてその理念を多くの人に広めることができるというものです。日本では「カスマターサクセスの青本」として知られる書籍の著者であるNick MethaがCEOであるGainsightは、カスタマーサクセスの本質を伝える上で欠かせない製品だと確信しています。
また私個人のワークとしても「THE MODEL」で描いた世界を実現するために必要なソリューションとしてこれまで働いてきたsalesforce, Marketoに加えて、Japan Cloudで関わることになったXactly, Gainsightで全てのピースが揃うことになります。そういった意味でJapan Cloudとしてだけでなく一個人としても今後の日本での普及に尽力したいと思います。
【求人】福田康隆×富士通。停滞する営業組織を、どう変えるか
福田 康隆ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長
昨年7月以来のアップデートも兼ねて富士通様と対談させてもらいました。
大企業は既存ビジネスが大きいので、どうしてもそこに依存してしまい新しい成長の芽を育てられないという課題が起きがちです。これは日本企業・外資系企業問わず万国共通ではないでしょうか。過去に大きな変革を遂げてきた企業は、そこで経営トップが腹を括って新しい領域に人を投資する。その領域を担当する人が不遇にならないように、評価・報酬設計を考えるなどさまざまな取り組みをして変革に導いていると思います。友廣さんと江尻さんのお話から、富士通の取り組みについていろいろと伺うことができました。

NORMAL

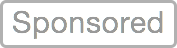











投稿したコメント