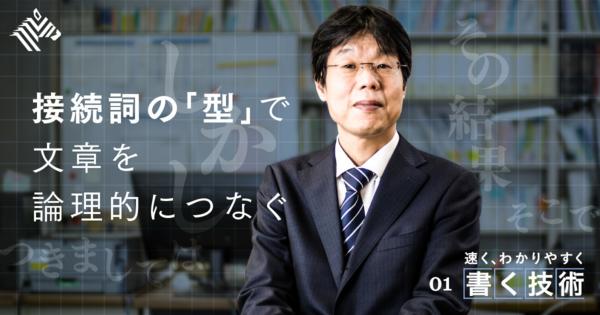【書く技術】接続詞「4タイプ10種類」で文章を速く、わかりやすく
コメント

選択しているユーザー
前後の内容を修正すると接続詞も変更することが出てきてしまう。接続詞の使い方の型は勉強になります。
更に知りたいのは、「助詞」と「修飾語」の使い方。助詞が変だと一文書いた後に違和感がある。ぴったりな助詞がスムーズに出てこない時の発見法を知りたいです。
修飾語は日本語の特徴と思いますが、結論が最後に来るので、どこで修飾語を置くかで、何に掛かっているのかかえってわかりづらくなる。修飾語を抜いた方がスッキリする場合も多い。という、これの使い方を教えて欲しいです。と思いながら、自分のコメントは読みにくいと思いました
注目のコメント
特集「速く、わかりやすく書く技術」を本日から5日連続で公開します。これまで読んだ文章術本の中から、私が最も参考になった本の著者の方々に取材して直接教わりました。
第1回は、接続詞で文章を論理的につなぐ。4タイプ10種類ある接続詞の用法と、「型」に沿って書く方法を、日本語研究の第一人者である石黒圭さんが伝授します。
【特集の概要】
「書くスキル」はビジネスパーソンにとって必須スキルです。コロナ禍のリモートワークによって、対面でのコミュニケーションが減り、オンラインでのやり取りが増えたため、「書くスキル」の重要性がますます高まっています。
しかし、多くのビジネスパーソンは日本語の文章を「書くスキル」をわざわざ習ったり鍛えたりしたことがありません。
そのため、ビジネスの文章を書くこと自体のハードルが高く、書き上げるのに時間がかかってしまいます。書いた文章はビジネスの相手に伝わりにくく、目指す成果をなかなか上げられません。
これは書き手にとっても、読み手にとっても、非効率・非生産的です。互いの時間と労力の無駄たるや計り知れません。
そこで、この特集で「速く、わかりやすく書く技術」を紹介します。内容はとても良いのですが,一点,論文・レポートの型の部分が,僕が学生にかなりの頻度で指摘する書き方になってしまっているので,そこだけコメントします.
論文は,基本的に過去の成果を否定しない,というのが大前提です(少なくとも私の分野では).なので,ここにあるように,「しかしこれまでの研究では〇〇はやられていない」というような書き方は基本的にはNGです.
これがNGな理由は3つほど考えられます.
1つは「やられていないことをやる」ことに価値があるとは限らない,という点です.やられていないというのを理由にして,なのでやりますという主張は,実は何の説得力もない主張になることが多いです.
2つめの理由は,そもそも先行研究はほとんどの場合対立する存在ではないためです.論文というのは自分の解きたい課題の範囲を明確にして,その範囲内で有効なことを検証する,というのが基本です.「これまでに〇〇がやられていない」というときは多くの場合,先行研究でその範囲を対象としていなかった,ということです.つまりそれを先行研究で取り扱わなかったことが問題なのではなく,自分が新しく問題をそのような視点で切り取ったというだけなわけです.別の視点から問題を見ている人に対して,その視点は間違いだ.こっちが正しい.と主張する必要はなく,自分はこの切り取り方をしたことで,こんな問題の解決法を見出しました,と言えばよいのです.
3つめの理由はもう少し泥臭い話ですが,論文は,その分野の人が見て査読してというプロセスを経るため,仮にその否定された著者が査読をするようなとき,正直あまりいい気にはなりません.もちろん中立的に査読はなされるべきですが,否定されればやはり厳しい目で見てしまうというのもある話なわけで,それもあって,基本否定はNGなのです.
ということで,先行研究に対して,「しかし先行研究では〇〇がなされていない」というような書き方をしなくても自分の研究を位置づけることは出来るのですが,学生が最初に論文を書くとき,ほぼ100%この書き方になります.
否定しない書き方というのも,できれば高校で伝えてほしいなとそんなことを思いました.
なお,この話は論文の書き方の話であって,ビジネスでのプレゼンなんかではまた違うのかもしれません.競合他社が出来ていないところを明確にするというのは大事かと思いますので.文章を書くという行為は、実はとてもエネルギーを要するもので、私自身結構筆が遅いなぁと悩んでもおりました。
何度も読み直しては接続詞を変えてみたり、代名詞を使って重複を避けたり、冗長過ぎないように文を区切ってリズムを作ったり。なんとなく感覚的にやってきたことが、こうして解明されるのは楽しいし、興味深いですね。
そういえば作家の藤原正彦さんは、ご自身が数学家であるにも関わらず、しきりに「国語を学べ」と説いています。
その理由の一つが、論理的思考力の形成であったことを、ふと思い出しました。