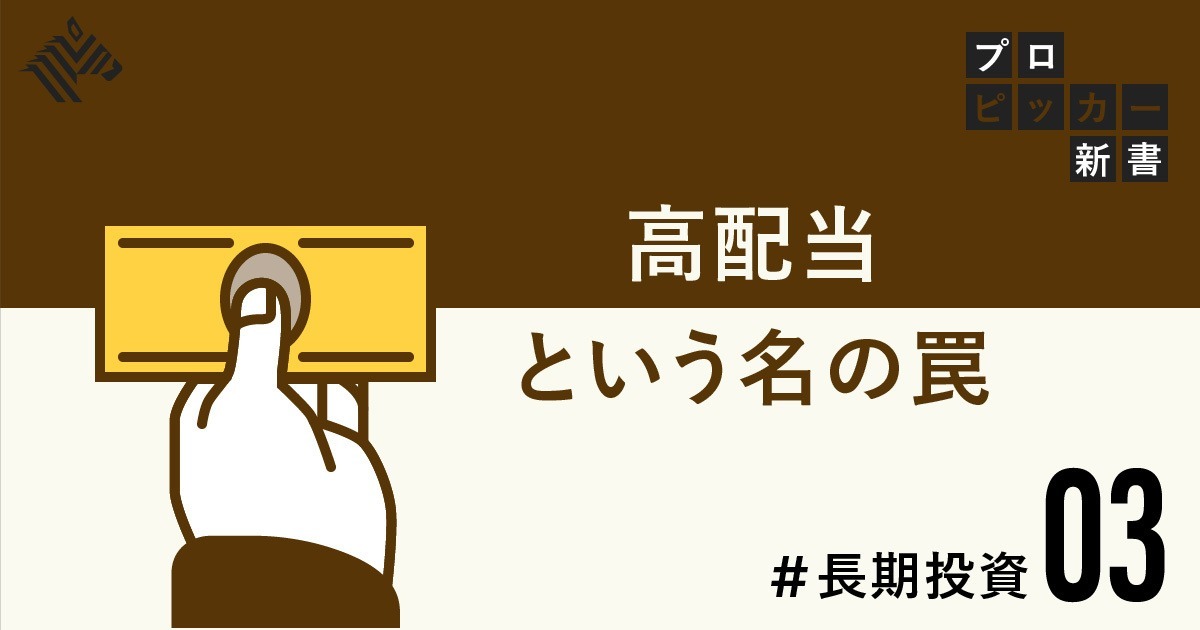【盲点】長期投資で「やってはいけない」3つのこと
コメント

選択しているユーザー
かつては、高配当の会社は投資先がないのかなと考えていました。
ですが、配当で生活するような人もいることを知り、株主にも様々なタイプがあることを理解しました。
配当性向をどうするかもまた企業からのメッセージ。
注目のコメント
だいたい次の3つが長期投資出来ない典型的な例です。
<その①>
「投資なんてお金が出来てから」という人が将来、退職金で投資を始めるという「やってはいけない」ことをやるハメになります。
<その②>
「投資なんて分からなくて・・・」という人は、投資のことを「相場の当てゲーム」だと勘違いしている人です。勿体ない。
<その③>
「配当欲しいわぁ」という人の気持ちはわかりますが、投資とは自分より優秀な経営者や素晴らしいビジネスモデルにお金を預けて長期的に儲けてもらうことです。配当や利益確定でチョコチョコ引き出すのは勿体ない・・・「高配当」の定義を明確にしておいた方が良いですね。ここでは配当性向が高い企業を例に挙げていますが、これよりも配当利回りで議論した方が分かりやすい。
・配当性向:配当支払額 / 当期純利益 ( = DPS(一株当たり配当額 / EPS(一株当たり利益)
・配当利回り:DPS / 株価
配当性向は企業が1年間で稼いだ利益のうち、何%を株主に還元するかという指標。一方で、配当利回りは投資した額(=株式の価値)に対して何%が毎年配当で受け取れるかというもの。
配当性向は企業(財務)の視点、配当利回りは投資家視点で見たもの。配当利回りは、株価が低迷するほど高くなる、株価低迷+配当をし続けている(=魅力的な投資先がない)というケースも多く、本稿の趣旨にも合致する。
成長と収益性の軸の4分類:
1)高成長・高収益
2)高成長・低収益
3)低成長・高収益
4)低成長・低収益
3)4)は割安銘柄になることが多く、配当性向の観点ではそれぞれ高い可能性がある。4)は財務余力が小さく内部留保を優先する可能性が高いため、理屈上は3)のカテゴリーが最も配当性向が高い傾向。
旧来日本企業はこの区分に入ることも多いが、足元投資マネーの二極化で注目されるのは、旧来産業 v.s.GAFAなどの新産業である。足元の株式市場の相場上昇も高成長企業に依存する部分も大きい。
1)2)のカテゴリーの区分がより重要になるが、先行投資フェーズで低収益であるが、高成長というカテゴリーであれば、無配当であるケースが多いだろう。これは高配当とはいずれの定義でもいえない。一方で、Appleなど成長性と収益性が共存する勝ち組企業の場合、1)高成長・高収益というケースが多い。高配当=配当性向が高いと定義すると、Appleは高配当企業だが株価リターンでも魅力的な投資先であることは明らか。
高配当=配当利回りと定義すれば、Appleの配当利回りは0.59%に過ぎない。配当利回りが3-5%という企業がざらにあることを考えると、高配当とはいえない。
加えて、米国企業は日本企業よりも圧倒的に自社株買いによる還元を重視している点も重要。Appleは配当性向は25%程度でコントロールしているが、自社株買いを積極的に行うようになっており、自社株買いを含めた総還元性向は直近150%を超えている。まさに「高還元」銘柄である。昨日テレビで池上彰さんが投資を解説する番組やってましたので、池上さんの番組ですら投資を扱うようになっているということは、そろそろ株価もいい水準まで来ているのではと思ってしまいました。