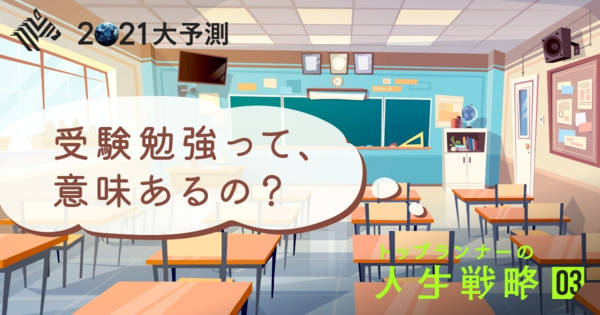【独占】アタマプラス×立命館、新しい「大学入試」をつくる
コメント
選択しているユーザー
企業の新卒採用でSPIのみで採用判断している例は、ほぼ皆無だと思います。面接や本人の志望理由書などで、人物全体を把握しようとするのはごく自然なことです。
一方で大学の一般入試は知識のみの評価です。そしてその形が社会的にはスタンダードだと見られており、面接や志望理由を課すAO入試の割合が高まることには、眉をひそめる人も多くいます。それはAO入試をはじめとする総合型選抜の形が充分に確立していないということでもあると思います。
アタマプラスが入試に踏み込むことで、全く違う角度から入試が変わってくるようになると、高校での教育も遠慮なく振り切っていける可能性が見えてきます。この動き、とても期待しています。
そしてアタマプラス、塾に限らず学校でも導入できるようになってほしいなと思っています。
注目のコメント
ペーパーテスト一発入試だけでは、受験生のことはわからない、それはそうです。ではどうすればいいのか、外国の大学も参考にしながら、日本の大学はこれまで20年間くらい試行錯誤してきましたが、まだ答えは出ません。
AO入試というのも増えましたが、アメリカ式の、書類審査でボランティア経験や部活活動を評価して、親の寄付金などもモノを言う、というような、親が金持ちなほど大学へ行ける、という仕組みがいいともいえません。
面接はどうかというと、面接で舌が回ったからといって、大学の授業で優秀かというと、全然そうではない例もいくらでもあります。
結局、1人の人間のことは簡単にはわからない、というあたりまえのことです。
立命館大学は、「政策科学セミナー方式」という入試方法もとられています。ある課題について、まず受験生に講義を受けてもらい、その後、解決方法を立案してもらって、それを採点する、というやり方です。単なる面接よりも、大学の授業への適性を計るうえでは、有効なやり方だと思います。
この記事で出てくる入試についての考え方は、学習の「習熟度」あるいは「到達度」といわれるものが、カギになるコンセプトでしょう。現在の教育行政では、高校までの授業でも大学の授業でも、一定の「習熟」「到達」が必要であるとされていて、それが単位・卒業の用件となります。習熟の度合いを計測するのは簡単ではありませんが、多くはテストやレポートを使います。
この記事で出されている案は、学生の学習をオンライン上で常に記録すれば、習熟度合いを正確に数値化できる、ということでしょう。そうかもしれません。あるいは、見逃されるものが多くあるかもしれません。厳格に評価されるようになり、お情けで単位を出すようなことはできなくなるでしょう。
マイナンバーカードに、学生の学習を常に記録し続けて、大学や企業が人材評価に利用できるようにする、という政府案もあります。基本的には、中国政府の教育・人材管理行政と非常に近いです。日本式の「デジタル化」を追求すると、中国式に非常に近くなるのでしょう。昨日、京都は立命館のキャンパスで、興味深い記者会見が開かれました。教育テックカンパニー、アタマプラスとともに、新しい「大学入試」をつくる実証実験を始める、というものです。
アタマプラスについては、1年半前に注目し、特集したスタートアップ。
https://newspicks.com/news/3885569
代表の稲田さんに、その舞台裏と狙いをNewsPicksが独占インタビューしました。教育は国家百年の計と申します。
これまでのシステムの中でもいいものはちゃんと評価して残し、改善できる点はきちんと考えていくというのが大事だと思います。
なにを当たり前のことを、とお感じの方もいらっしゃると思います。教育はその子の人生がかかっている重要なものなので慎重にならざるを得ないのは理解しますが、逆に極端な事なかれ主義や平等主義に足を引っ張られていないか?と思うこともあります。