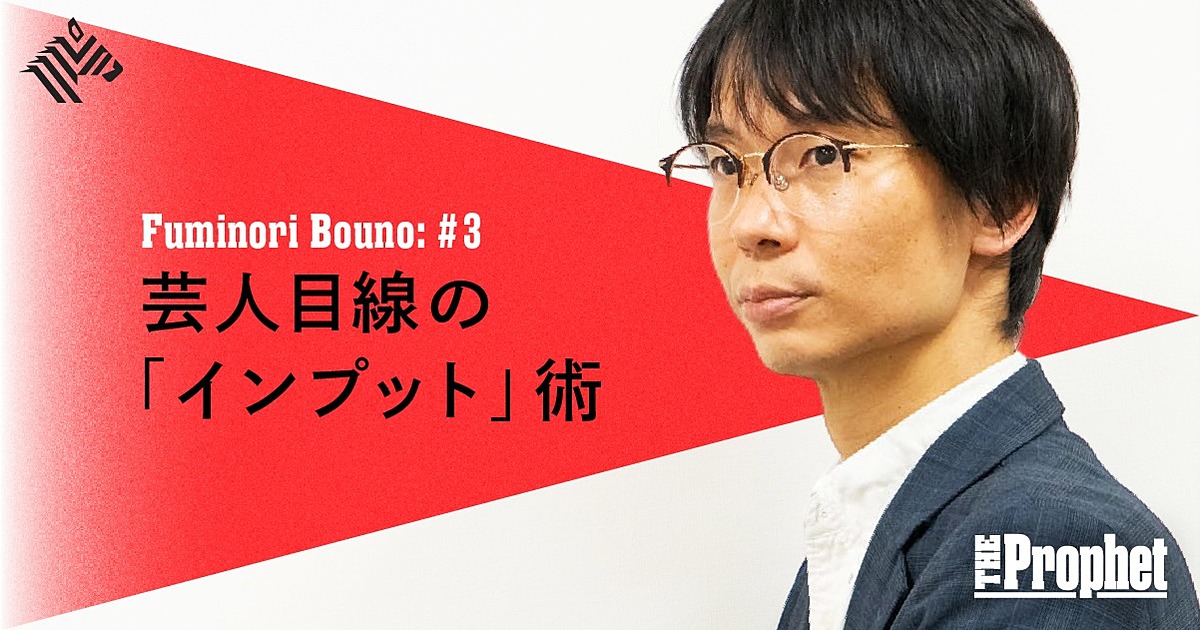【房野史典】「しゃべれない知識」は武器にならない
コメント
注目のコメント
吉本芸人のブロードキャスト!!房野と申します。
拙著「13歳のきみと戦国時代の「戦」の話をしよう」のインタビュー記事、最終回となります。
NewsPicksの読者諸賢には分かりきった話で申し訳ないのですが、
「歴史ってこんな風に活用するのがいいんじゃないかしら?」
ということを喋っております。
もうこれ以上広げられないというくらい、心を広くしてお読みくださいませ。「僕にとってのインプットは、主に「ここが知りたい」という情報を探しながら読むという作業です。」目的を持って本を読む。何か決まっていたら、それが効率的ですね。
同志社中学校の先生から今年の夏休みの課題について話を伺った際、次のようなエピソードを教えていただきました。
課題についてある生徒と進捗のzoom面談をしている際に、推薦図書を何冊か提示したところ読むスピードがかなり遅く感じたことがあったそうです。そこでその生徒に聞いてみたところ、「最初から最後まで全部読んでいるので、読み終わらない」とのこと。そのため、その先生は最初に目次を見て、必要そうなところを読んでみたら?と提案したそうです。
目的を持って読んでいたと思いますが、「手法」という観点も重要なのだと改めて感じました。目次を最初に読んで当たりをつけるというのはよく言われることではあります。ただ、私たち社会人でも同じようなことをしてしまう人、多いのではないでしょうか。そう考えると、中学生の時にそのようなアドバイスをもらえるのはとても羨ましいです。未来を予測しようと思っても、わからないことのほうがほとんどです。しかし、過去にどのような因果関係で、何が起きたかを学ぶことはできる。新しいものを作ろうとする人ほど、歴史に立ち返るのが大切なのだと思います。