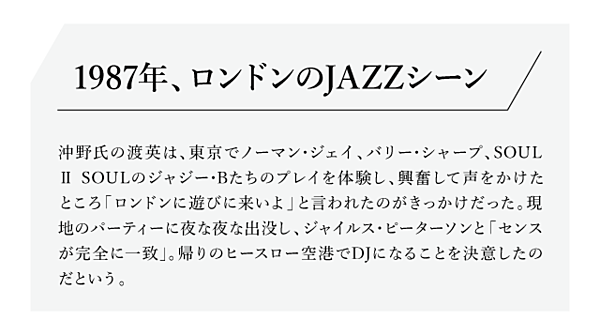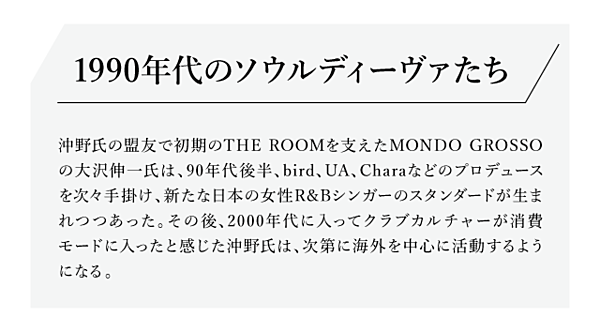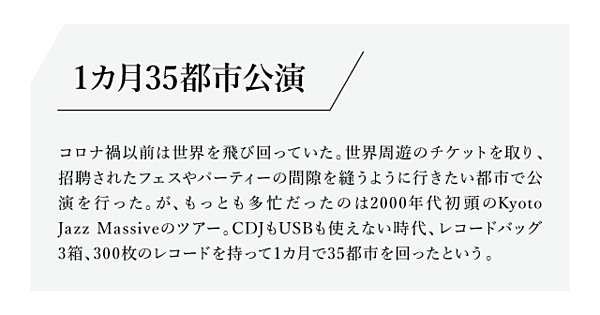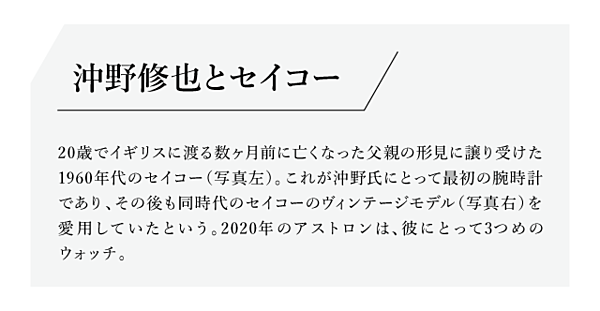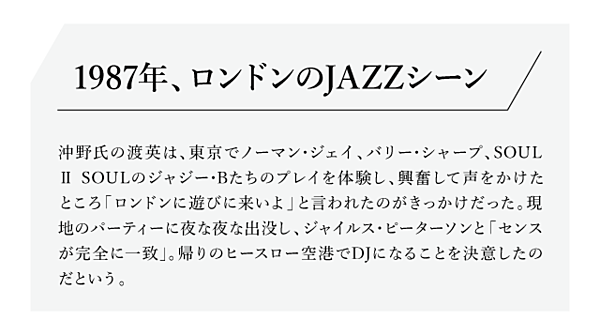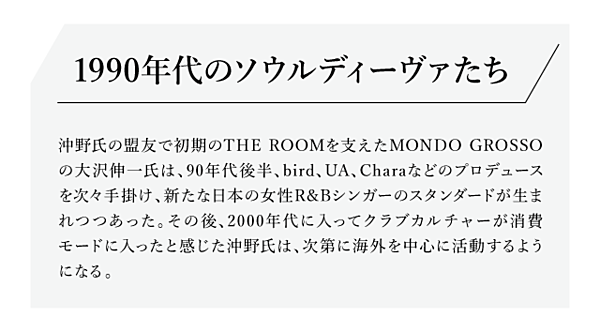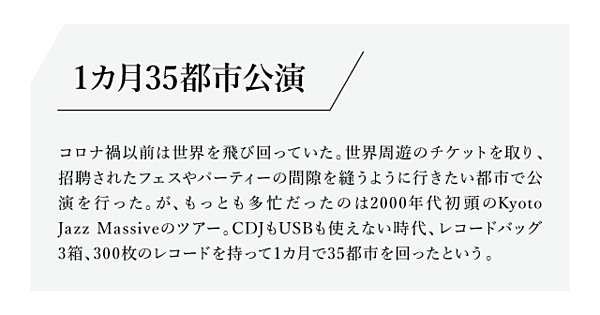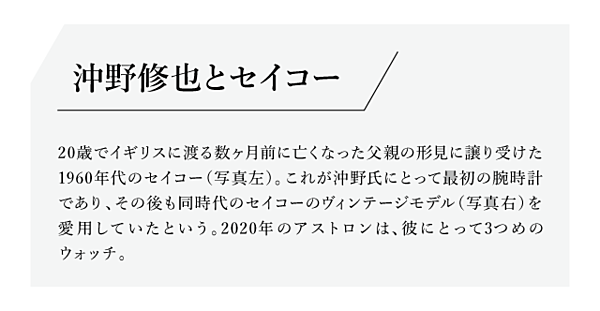2020/11/24
【沖野修也】異質なものの「間」から、100年先のスタンダードが生まれる
NewsPicks Brand Design / Chief Editor
「JAZZ×ダンス」の衝撃
── ジャズって、なんだか難しい音楽だというイメージがあります。
一般的にはそうかもしれませんね。歌も入っていないし、メロディも頭と最後にしか出てこない。途中は抽象画みたいなアルバムも多いですから。
僕も、最初はグラフィックから入りました。高校時代、ブルーノートのアートワークがカッコいいなと思って聴き始めたんです。友だちが日本語のロックを聴いているときに、僕はひとりでジャズ。背伸びしたい時期でもあったんですね。
その後、1986年の雑誌『宝島』に載っていたジャーナリストの花房浩一さんの一文に衝撃を受けました。
「ロンドンでは若者がジャズで踊っている──」って。
当時、日本のクラブでかかる音楽というと、流行している曲をダンスフロア向けに加工した「12インチバージョン」が主流でした。みんなが知っているヒット曲だから盛り上がる。
そんなところでジャズがかかって、誰がどう踊っているのか。僕は自分で体験しないと納得できない質なので、就職活動しないといけない大学4回生の春に、1カ月休学してロンドンへ行ったんです。
── ロンドンのクラブはどんな感じだったんですか。
国籍も職業も人種も本当にごちゃ混ぜで、おもしろくてカッコいい人たちが集まって、垣根もなくコミュニケーションしていた。初対面の日本人である僕にもどんどん話しかけてくるし、あの人カッコいいなと思ったらこちらからも声をかける。
まず、そんな場所のあり方が衝撃でした。その輪のなかに自分が入れていることに感動して。
しかも、ずーっと僕好みの曲がかかり続けているのに、知っている曲はひとつもないんです。「すごくいい! 次どんな曲がかかるんだろう? うわ、これもめちゃくちゃいい!」が続く。
アフロアメリカンの系譜を受け継ぐソウルやファンクのようなリズムがベースとしてあるようなジャズ。それが次々提案されるような選曲。まさに“洗礼”でした。
── それが、沖野さんのキャリア30年の原点なんですね。
ええ。僕は音楽だけでなく、ロンドンのクラブカルチャーをまるごと持ち帰りたかったんです。インディペンデントな人が集まって自由にコミュニケーションできる場所を、日本にもつくりたかった。
それには僕の立ち位置も重要でした。僕が音楽のキャリアをスタートさせたのは、実は京都にあった「コンテナ」というクラブの「DJ兼雇われ店長」だったんです。
その頃、日本のDJは、あまりお客さんとしゃべらなかった。お客さんに遠慮があったり、DJのアーティスト気質によるものだったりするんですけど、僕はどんどんしゃべって客との距離を縮めていました。だって、DJであるより前に、お店のスタッフですから。
このスタンスは、のちに僕が渋谷に開いた「THE ROOM」にも引き継がれています。
音楽が生まれる現場のリアリティ
── 単に選曲するだけでなく、場を取り仕切る「ホスト」であることは、沖野さんの音楽制作にどう影響していますか?
僕のなかで「場所と表現」は一体化しています。活動を続けるうちに作曲やプロデュースも手がけるようになりましたが、最初は「DJが曲をつくるなんておこがましい」と思っていたくらいですから。
いわゆる「アーティスト」は、自分のなかから湧き出るものや、ときには社会の問題などを題材に曲をつくりますよね。でも僕はまず、その音楽が流れる場所や、聴く人を想定します。
── コミュニケーションが重要なんですね。
そう。人と人、音楽と音楽の間から新しいものが生まれる。
DJの仕事って、場所や客層に合わせて、異なるジャンルやアーティストの音楽をつないで、新しい文脈に再構築することなんです。
たとえば、ジャズからブラジル音楽、あるいはパンクからテクノにつなぎたい。そのブリッジとなる楽曲を発掘するのもDJの仕事なんですが、どうしても見つからなければ、自分でつくるしかない。
異なるジャンルの間を埋めるピースがまだどこにもないのなら、それこそが、僕がつくるべき音楽だなって思ったんです。
── その現場として、渋谷の「THE ROOM」も多くのアーティストに愛されてきました。
そうですね。1990年代後半にはジャズシーンもえらく急角度で成長し、僕や盟友の大沢伸一くん(MONDO GROSSO)がJ-POPのプロデュースに携わって、それなりの影響力を持つようになった。
当時は景気もよかったから、レコード会社にも野心あふれる人たちがいて、アンダーグラウンドとメジャーの協業が成り立っていたんです。本来、交じり合うことのなかった2つの業界が一体になったときのパワーは本当にすごかった。
僕らも、日本語をどうやってビートに乗せればカッコよくなるか、死ぬほど考えて試行錯誤していました。
クラブの現場と創作、日本と海外、アンダーグラウンドとメジャー。そうやってあちこちを行ったり来たりしてきたから、これだけ長くひとつのことを続けられているんだと思います。
DJとは「コミュニケーター」である
── 沖野さんは初期から世界志向だった印象があります。
頻繁に海外へ行っていたので、否応なく世界が基準になったと思います。多いときは、1カ月で35都市公演ですからね。途中で弟と分かれて、ひとりずつDJしたからなんとかなったんですけど。
京都にいようが渋谷にいようが、世界中の音楽は聴けますよね。情報として入ってくるものに差異はありませんが、現地に行って、お客さんの反応を肌で感じないと得られないリアリティやディテールがあります。
── 街によって、どんな違いがありますか。
たとえばヨーロッパでも、ロンドンはソウル、パリはアフロ、ベルリンはテクノでバルセロナはラテン……みたいに、ベースとして聴かれている音楽の傾向がそれぞれに違います。
それに、フロアの反応や一体感って、その国や都市の社会的な状況も影響しているんです。
僕はこの10年ほど東ヨーロッパによく行っているんですが、あのあたりは内戦が終わってまだ20年しか経っていないから、日本でいうと1965年くらいの状況に近い。クロアチア、モンテネグロ、ベオグラードとか、めっちゃ元気。もう上しか見ていない。
そういう状況って、街を歩いたり現地の人と話したりしないと実感しにくいじゃないですか。そのうえで、この街ではどんな音楽がウケるかを考えて、フロアの反応を見ながら調整していく。
── 何を見て、どう調整するんですか。
1曲かけると、如実に反応が表れます。ほかの都市や別のクラブで大ウケした曲がまったく刺さらないこともよくあります。
そういう反応を読み解いてどう立て直すかが、DJの腕の見せどころであり、コミュニケーション力です。
僕がフロアを見るときにいちばんこだわるのは、お客さんの「滞留時間」です。もちろん客数は増えてほしいし、欲を言えば、アンコールが鳴り止まないとさらに嬉しいですけどね。
DJがコントロールできるのは、居合わせた人をどれだけ自分の世界に引き込めるか。客数はそこそこだったとしても、集まった人たち全員に、最後まで残ってもらいたい。それが僕にとっての成功です。

沖野修也氏が着用している時計が「Seiko Astron Global Line 5X series SBXC065」。1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウォッチ「クオーツ アストロン」の流れを受け継ぎ、2012年、世界初のGPSソーラーウォッチとして誕生。ブランドのルーツである「絶対精度の追求」と、それを実現するための「絶え間ない進化」を体現したグローバルモデルだ。
── 世界で場数を踏んで、見える景色は変わりましたか。
いろいろな違いを見てきたことで、時代や場所を越えて世界中の誰にでも届く音楽を抽出したいという気持ちは強まりましたね。
日本のクラブにも様々な人が来ますが、海外ではもっと、人種や年代、ジェンダーから文化的なバックグラウンドまで、本当にバラバラなんです。
それぞれのアイデンティティを薄めて最大公約数をすくいとるのではなく、すべてのエッセンスをごった煮にして凝縮し、普遍的な音楽を抽出したい。
それは僕の個人的な使命感でもあるし、「Kyoto Jazz Massive」の大きなテーマでもありますね。
実験し、変わり続けるのが「JAZZ」
── 普遍的であり、根源的な音楽ですね。一方で、時代ごとの変化についてはどう考えていますか。
現代のジャズが確立したのは1960年代だとして、ルーツをたどれば20世紀初頭のアメリカ南部に、さらにさかのぼるとヨーロッパの近代楽器やアフリカ音楽へとつながっていきます。
僕がリスナーとして聴いてきたなかでも、ジャズは派生と融合を繰り返して時代とともに変化し続けています。いくつかの決まり事はありますが、それさえクリアすれば、実験的なアプローチを含めて自由な表現ができる。
Kyoto Jazz Massiveも「JAZZ」を名乗るからには、その実験を継続し、つねに今の音楽をやり続けたい。1960年代以降のジャズが時代ごとにアプローチを進化させてきたように、今を更新し続けるから、あとから振り返ったときに「1990年代のKyoto Jazz Massive」「2020年の沖野修也」と語られうると思うんですよね。
── そうですね。前と同じじゃないから、新譜を買ったりライブに行ったりするわけですし。
僕は、Kyoto Jazz Massiveを100年続く「ブランド」だと考えているんです。
僕がいなくなったあとにクリエイティブディレクターやメンバーが替わっても、同じ精神性に基づいて音楽やパーティーを続け、時代に合致した表現を発信していくような。
このセイコー アストロンが、セイコーが築いてきた信頼のうえで「スケールを拡張しよう」とメッセージしているように、Kyoto Jazz Massiveもこれまでの活動で得た信頼を背負って、新しいコンセプトやスタイルを提案してきた。
その姿勢とクオリティを認めてもらえたから、人やアーティストが集まり、新しい音楽を生み出せるんです。
── このアストロンも、ルーツをたどれば1969年に生まれた世界初のクオーツ式腕時計です。機能やデザインは異なりますが、技術を革新し、時間の精度を追求し続けるという姿勢を受け継いでいる。
その姿勢に対する信頼と共感ですよね。大事なのは。
実は僕、生まれて初めて着けた腕時計が、20歳のときに亡くなった父の形見のセイコーなんです。腕時計には精度や機能、デザインなどいろいろな価値がありますけど、僕の場合は自分のなかの誠意や信念を確認するガジェットなんですよね。
ものすごく個人的ですが、正確な時を刻むっていうセイコーのイメージと、生真面目で誠実だった父親の記憶がシンクロしていて、身に着けるたびに「いまの俺は大丈夫か?」と問われる感じ。
音楽も、そういうものではないでしょうか。人それぞれに思い入れがあり、聴くたびに記憶が蘇ったり、初心に立ち返ったりする。その時代、その場所のコミュニケーションから生まれたものが、楽曲や音源として定着し、繰り返し聴かれ続けるわけですから。
だから、手を抜けない。100年先のスタンダードをつくろうと思ったら、「今」のオーディエンスと「音楽が生まれる現場」を共有し、そこから嗅ぎ取ったエッセンスを表現する。できるだけ誠実に、新しい挑戦を続けていくしかないんです。
編集:宇野浩志
構成:武田篤典[steam]
撮影:小島マサヒロ
デザイン:月森恭助