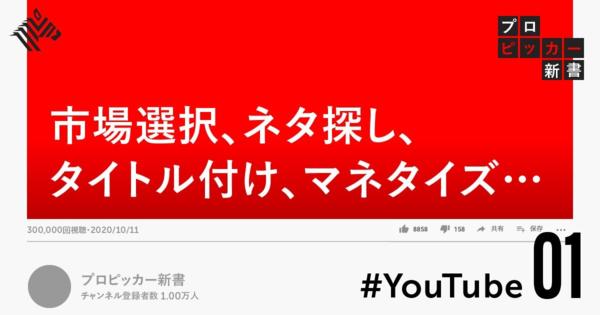【新】YouTubeを「戦略的」に配信するための全手法
コメント
注目のコメント
2020年のトレンドであるYouTube業界2.0=プロ市場への変化やそれに伴うBtoBのYouTubeチャンネルの成長、動画制作のフレームワークについて記事にしていただきました。
野村さんも触れているように、チャンネルの運営はまさに事業を運営するのと同じなのでカロリーはかかりますが、そこから広がるビジネスチャンスは非常に大きいものがあります。
YouTube特有のコンテンツの作り方の考え方はまだまだ一般的でないことも多いと思いますので今回の連載を通じてその一端を垣間見ていただき発見のある連載にできればと思いますし、最終的にはYouTubeチャンネルにトライする企業が増えると良いのではないかと思います。
皆さん宜しくお願いします!もはや「遊び」の枠を超えて、ビジネスの有効なツールになりつつある「YouTube配信」。今回、BitStar代表の渡邉さんに「これでもか!」というぐらい詳細に方法論を解説いただきました。これから配信される方も、既に配信されている方も、保存版として折に触れてお読みいただきたい内容です。
原稿を読んで実感したのは、どの市場を選ぶか、個々の動画の質をどう高めていくか、どのようにPDCAを回していくのか、という一連の流れは、まさに「起業」と同じだということ。「競争環境は自由、当たったら大きい」という特性も、アントレプレナーシップを持った方々を引きつけるのだと思います。
追伸:コメント欄でご指摘いただきましたが、「情報軸」「人軸」の図表の表記が逆になっておりました。お詫びして訂正いたします。なるほど、「情報軸」と「人軸」の2軸で考えるとわかりやすいですね。素人がキャラで売り出すのはむずかしい。ゆえに、まずは情報にエッジをきかす。
動画ならではの、わかりやすさを出す工夫がこのレポートにちりばめられています。