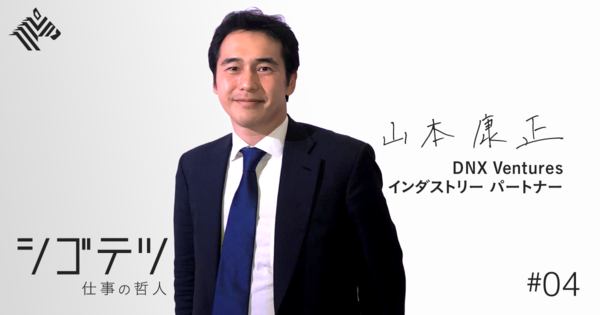【山本康正】いい情報はオープンではない。自分から取りに行け
コメント

注目のコメント
「いい情報はオープンではない。」
「人とのつながりは大事」
私も完全に賛同します。NP内でもしつこいくらい何度も発言していますし、若い人たちに「今後生き残るために必要なもの」を伝えるチャンスが有るときには常に「人脈と体力」というようにしています。
社会に出る前って、なぜか社会はオープンでフェアだと思い込んでしまうんですよね。そんなわけない。学歴だって職歴だってそこにいたことがすごいのではなく、そこで得た人脈のポテンシャルを評価されているのだと思います。
こういう話をすると、「だから日本は嫌なんだ。自分はフェアな海外のほうがいい。」と思われるかもしれませんが、自分の体感的には海外のほうがもっとウェットで人脈を大切にしているイメージです。国籍も受けた教育も宗教も人種も違う人達とやっていく上で人からの紹介というのは最重要ファクターの1つ。第4回は情報格差、10年前のシリコンバレーの話です。当時のシリコンバレーはUberもテスラの半自動運転もなく、大変不便だったのですが、それを体験していると、今や空港にはUberステーションがあり、そこら中にプリウスの感覚でテスラは走ってますし、充電ステーションも多くのショッピングモールに備え付けられています。その変化の驚異的なスピードを見ていると、テスラが世界最大の自動車会社であるトヨタの時価総額を抜いたのも理解できるので、一度住んでいたのは良かったなと思います。
よくシリコンバレーはディズニーランドと例えられますが、GoogleやFacebookのキャンパスで食事するという、まるで派手な「スプラッシュ・マウンテン」だけを見てわかった気になるのが一番危ないと思います。大事なのはその差分です。どこに何ができ、何が潰れていったのか、注意深く見る必要があります。もう一つ大事なのは京都の様なクローズドなネットワークです。どれだけ住むというよりも認められているかどうかで情報の入り度合いが違います。これも差分を見ないとわかりません。
この差はなかなかメディア、白書には出てきません。記者の方の多くはローテーションですし、特にTVでは出てこないでしょう。なぜならTV局のアメリカ支局はほとんどNY、ワシントンDCかLAにしかないからです。なので、2年に一度は自分で見に行って、その違いを見る必要があるのです。特に、この新型コロナで行きにくくなってはいますが、その間もテック企業は問題なくリモートで働いているので、変化は起こり続けています。見えない、伝わっていないことが、日本企業にとって長期的・将来的に大きな打撃にならないかと危惧しています。"いい情報はオープンではない"…全くの同意です。"知らない"=無知で損することも多く、情報から学び得ることはとても大事である。オンラインで簡単にアクセスできる情報にも役立つものがあるが、多くは既知のことを言い換えているだけだったりする…。オフラインの知識獲得機会の代表格である書店にて、諸々面白い本を探求することも素晴らしいことであるが、書店に並んでいる情報は、誰かが考えたアイデアや発見が綺麗に纏まり、出版されるまでのリードタイムを鑑みるとかなり古いものとなる…。本当にリアルに"生きている"情報は、オープンになっていない。自分からプロアクティブに取得する行動が求められる。ある領域の第一人者たる人間が持つ経験知・実践知を入手することは本当に容易ではない…。経験知・実践知には、その人の並々ならずの"苦労"や"苦辛"から得られた深い洞察、insightが含まれるからだ。相当の価値があるものだから、自らの行動が本当に必要になる。カンファレンスや会合などの機会にて、自らのアイデア、事案をぶつけて、フィードバックを得ることも多くの学びに繋がると思う。"この人に訊きたい!"と思ったら、自身のフットワーク、ネットワークを駆使して価値ある"学び"と"繋がり"を求めていきたいですね…。