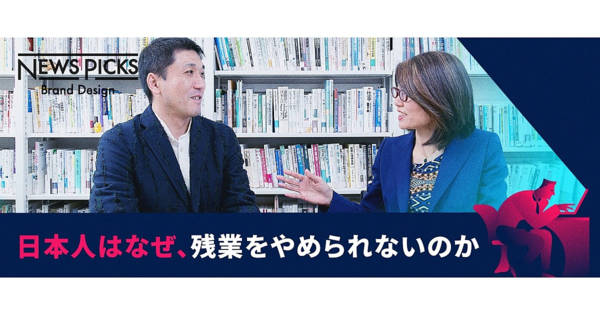時間の意識がイノベーションを生む、「働き方改革」の本質
コメント
選択しているユーザー
今の日本の状況でリモートワークとかをしても、余計生産性の概念がなあなあになって色んなトラブルが生じそう。マネージャー層もワーカー層も変革期に合わせてお互いにより良い働き方ができるように頑張りたいね。
注目のコメント
「どこから手をつけて、何をやめるのかを考えていかなければなりません。」に共感。
Start,Stop,Continue に分類。 その他には問題意識を持って日々の行動を見直す心の余裕とやめる勇気が必要。中原先生の一語一句すみずみまで賛同する元時間的ハードワーカーです。
----
残業ズハイ
残業における幸福感の背景にあるのは「有能感」や「没入感」。
つまり、「自分は会社に頼られている、優秀な人材だ」という思いと、「時間を忘れ、物事にのめり込んで、他が見えなくなる」感覚です。
>いわゆる“残業ズ・ハイ”といえる状態で、これはある意味、長く続けば依存症のようなリスクを持つものといえます。
----
先の仕事、将来のキャリアのための学びを後回しにし目の前の仕事を片っ端、からかたづける。
これに慣れてしまうと緊急度が高くないが重要度が極めて高い仕事が手付かずの状態になりいざその仕事の緊急度が高まったときに何から手をつければいいか分からなくなる。
受験前日にしてあたま真っ白というやつです。
リアクションは上手いが芸がない芸人のようなこと。
使い捨てされない人材になる唯一の策はリアクションをグッとこらえて芸を磨くこと。
暇人扱いされてもスケジュールすかすかでもいい、先のための仕事を選択し取り組むこと。毎日毎日夜中まで働いて忙しいけれど、すごく成長している気がするし、会社にも貢献して認められているから、もっともっと頑張るぞ!(エナジードリンク片手に)と思っている方には、ぜひ読んでいただきたい立教大学・中原淳先生と日立ソリューションズ伊藤さんの対談です。
「長時間労働はなぜ悪なのか」
「働き方改革を成功させるためには」
私も徹夜でなんとか帳尻を…と10年以上働いてきてしまったタイプですが、この働き方から抜け出すのはすごく難しいと感じています。
とくにリモートワークが広がっている今だからこそ、改めて「時間」の意識を強く持つ必要があると思いました。