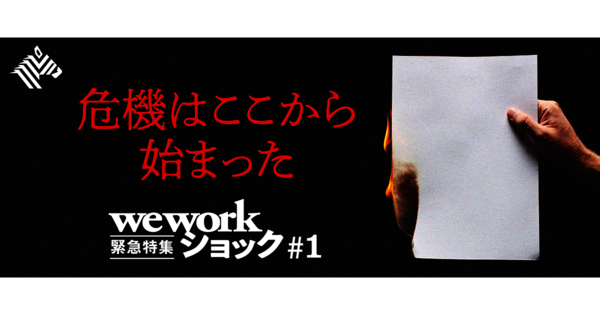【完全解説】知らないでは済まされない。ヤバいWeWorkのすべて
コメント

注目のコメント
これ本当に読み込みましたね。目論見書をここまで解説するメディア見たことないので、必読です。UBERに引き続きで、米国のIPO市場には影響を与え始めてるみたい。日本にも影響出てくるだろうと思います。
この問題は、そもそもビジネスモデルとしてどうなのか?という観点と、経営者としてガバナンスはどうなのか?という2つの別々の論点であると考えています。後者は、S1に確かに書いてある通り、モラルとしてどうなのよという事実があるのは間違いないけれど、スキャンダラスな話でただのネタでしかない。
それよりもビジネスモデルの方について、Weが志向したのは、現在市場を牛耳るIT大手のGAFAが不得手なリアルアセットビジネスであり、またメーカー等のリアルアセットビジネス大手や他の不動産大企業が簡単にできるわけでもない、両方の側面を持つハイブリッドな新しい分野であると考えています。営業赤字が続くUBERもこの類。
しかし未だ成功見本はなく、両方の知見と経営のバランスが求められるビジネスモデルだと思う。Weが立て直せるのかはわからないけれど、やり切って教訓を残していって欲しいなと思います。それにしても、あの手この手で、リアルアセットとテクノロジーを融合させようとするソフトバンクはやはりクレイジーな凄いチャレンジャーだと思う。批判で終わりにすることなく、学びとしたいと思います。今週は急遽予定を変更し、世界のスタートアップ投資の潮流の「転換点」を予感させる、「WeWorkショック」を緊急特集でお届けします。
初日の本日はショックの震源地となった、WeWork(The We Company)の上場目論見書「S-1」全383ページを徹底的に読み込み、その要点をぎゅっと落とし込んだスライド解説。投資銀行のIPO担当、米国会計士、不動産テック企業などあらゆる専門家たちの力を借りながら、特集取材チームで読み解いた力作です。
それにしても、志高き創業者のアダム・ニューマン氏はいつ頃から変節したのでしょうか。非常に残念でなりません。WeWorkのS-1をザーッと読んだ第一印象はズバリ
「アダム・ニューマン、セコいよ」
決算のルールで決められていなくても投資家にとって役立つ財務情報を会社が独自に計算して開示することはよくありますし、望ましいことでもあります。
ただ、WeWorkの目論見書で独自に開示されているContribution Margin(貢献利益)なる概念はメーカーが社内の管理会計で一般的に使っているものとも違うし、どんな狙いでどんな根拠を持って開示しているのか、まったく意味不明です。
そもそも同社のコストは、ほとんどが固定費だと思うんですね(固定費と変動費については誤解が少なくありません。増えたり減ったりするコストが変動費、不変なコストが固定費ではなく、操業度や販売量、売上高によって比例して変動するのが変動費、それらに関係なく決まるのが固定費です)。
Contribution Margin(貢献利益)なる概念を持ち出しているのは、どうにもならない巨額の赤字を何とかして好材料に見せるための涙ぐましい工夫ですが、その計算プロセスを何度吟味しても意味不明過ぎて、セコいという感想しか湧いてきません。
また、公私混同な取引はニューマンさんセコいよと思うと同時に、こんなものをよく目論見書に載せるなあと驚きを隠せません。
普通、こんなもんは目論見書に開示するんではなく、主幹事証券や弁護士が経営者に迫って取引そのものを解消させるでしょう。それがイヤだったら上場なんてやめときなさいと。
本件は特殊なケースだと信じたいですが、マーケットを取り巻く人たちの品位が乱れていると感じます。