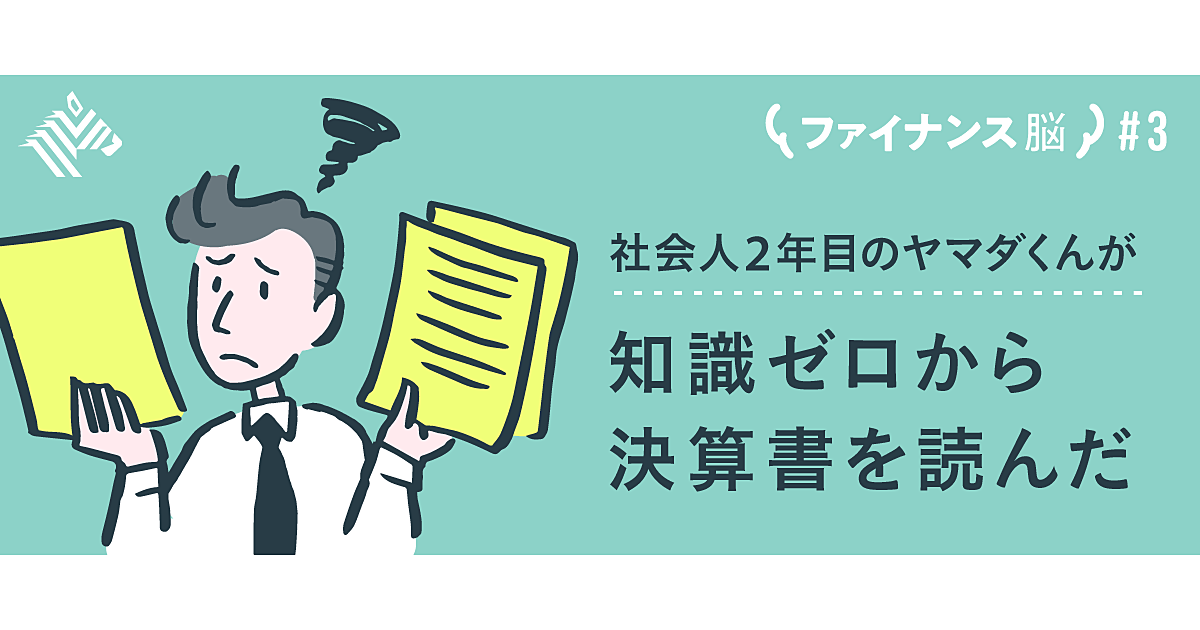【完全図解】ざっくりつかむ。会計・ファイナンス「超入門」
コメント

注目のコメント
以前の会計2.0特集にあった超秀逸な財務三表入門をさらにソフトにした感じですね。財務三表入門も含め、大学生はみなさん読んだ方がいいくらい、よくできていると思います。あと可愛い。
https://newspicks.com/news/3106388/
よりターゲットとなる読者を広げたからだと思いますが、個人的には、前回の記事の方が理解しやすかったです。
例えば営業利益は事業モデルを考慮せずに業界またいで横比較してもあまり意味がないとの認識です。また、PL上の利益を出さずに成長し続けている企業が総じて悪く見えてしまうのはあまりいただけないかなぁと。このあたりは今後の記事で回収されるのかもですね。
企業の比較も、前バージョンは任天堂、東芝、シャープ、トヨタ自動車、ソフトバンク、マネーフォワードといった顔ぶれで、財務諸表から企業の実態を想像する練習としては、秀逸な取り合わせだったと思います。
とはいえ、今回の記事も会計に全く取っ掛かりのない人にとっての入門編としては十分だと思いました。(なんか上からですみません・・・)「インフォグラフィックで分かる決算書の読み方」です。手前味噌ですが、黒田デザイナーが描いたキャラクターが絶妙にかわいいです。内容は、財務3表が全く読めない人にもとにかく分かりやすく、をコンセプトに作りました。
主人公のヤマダくんと先生役のロボットが絶妙なので、今回のコメント欄で好評だったら、学ぶ系のインフォグラフィックコンテンツをシリーズ化したいな、なんて思っています。会計・ファイナンスものの中級編もありですし、経済学とかも面白そうです。
実は、財務3表のインフォグラフィックについては、昨年も頑張りました。見比べていただいても面白いかもしれません。
■NewsPicks編集部オリジナル記事
「【新図解】知識ゼロから学ぶ「財務3表」のすべて」(2018年6月20日付)
https://newspicks.com/news/3106388/記事に加えて、いくつか理解のために重要な点を。
【財務三表はつながっている】
例えば自動車を現金で買ったとして、数年使うとする。この場合、これはどう計算するのがよいか?
買った瞬間に現金が出る。これはBSでは現金が自動車に代わる(資産の種類が変わる)、そして投資なので投資CFでそのお金が出る。でも数年間使うのだから、使う分だけ毎年費用としてPLで減価償却費用を計上する。また使うほどに中古価値は下がるので減価償却費用分だけ資産を減らしていく。
こんな感じに、三表はつながっている。
【BSは「誰の権利」と「時間差の吸収」】
BSは、本記事にもあるように資産がお金をどう使っているかと、負債・純資産がそのお金をどう集めたかというのが一般的な説明。ただ個人的には最近は「誰の権利」という言い方の方がしっくり来ている。
というのは、企業間の取引では「ツケ」(売掛金・買掛金)が多い。これはお金を集めた・使ったというより、自分に権利があるのか、相手に権利があるのか。
そして、「ツケ」は時間差だし、上記の車を買った時の資産計上と使用する期間、減価償却も時間差。こういった時間差をBSを使って吸収する。
【資産計上されない資産がある】
例えば広告を打ったとする。広告は費用でPLには計上されるが、資産にはならない。でも広告で使い続けてくれるか、それとも一瞬使って終わりになるかで効果は全く違う。
会計ルール上、資産になっていないがこういう実質的な資産がある。資産なのだから価値が存在し、それが顕在化するのが買収。それが「のれん」というものが発生する背景。でも思ったほどその価値がないと「のれん減損」というものも発生する(昨日の日本電産でも出てきた言葉、日本電産はそれがなく適切に買えているということ)。
記事に加えてコメント欄も!また昨年の同様の特集(①)や、以前SPEEDA総研(②が5回連載の一回目)でやったものも併せてご参照いただきたい。
①https://newspicks.com/news/3106388/
②https://newspicks.com/news/1027661