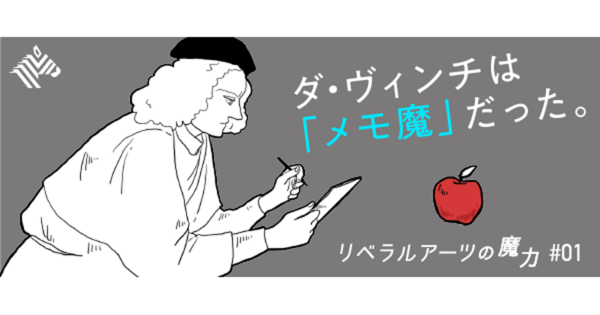【イラスト解説】ダ・ヴィンチを天才にした、すぐ役には立たない「10の習慣」
コメント
選択しているユーザー
現代のメモ魔。前田社長を題名で思い出しました。
読んでから感じたのは【学力、偏差値】って測りは思った以上に色んな力が結集されて出来ている。
今現在【SNS発信力】等々いろんなものを測ることに人は時間を使っているが本当にすごいものって測ることすら、出来ないのではないのかなんて思ったり
注目のコメント
「普遍的人間」というのがイタリア・ルネサンス期の理想的な人間のあり方とされていました。東京大学の入学式で「メタ知識」というのが話題になりましたが、そこでいわれたのは、大学というのは特定の技能、料理とか運転とかプログラミングとかのやり方(know-how)を学ぶところではない、そうではなく、「メタ知識」、つまり何をやるのにも応用の効く普遍的な知を学ぶところであるということです。普遍的な知(ある物事を深く理解する人文社会諸学know-what、ある事象がなぜ起こるのか理解する科学know-why)を身につけてこそ、社会全体に長期に渡って必要なことを理解し、新たなknow-howを創案することもできる、という話です。
大学Universityというのは普遍的Universalな知について学ぶ場としてヨーロッパで発展してきました。これは、「普遍的な知」が存在するというヨーロッパの世界観に基づくものです。「普遍的な知識」が存在するというのはキリスト教とも密接に結びついた考え方で、世界は全て神によって創られているのだから、全ての知識には関連性があるという発想です。数学は物理学や経済学に応用できる、化学は生物学に応用できる、というこの考え方は近代西洋の躍進の基礎でもあります。
レオナルドは、ルネサンス期、つまり「普遍的な知」を美術や手工業、都市設計、機械へと応用しようとしていた時代のあだ花のような人です。「普遍的な知」の他分野への応用はこの後急速に進み、大学も急速に変わって社会で大きな役割を果たすようになります。この変化は後にデカルトやライプニッツ、ニュートンらによって決定的になりますが、レオナルドは時代が早すぎたのと数学に弱かったこと、そしてラテン語ができなかったこと(これは、当時アラビア語、ギリシア語からラテン語に翻訳されつつあった最先端の自然科学書が読めないということでもあります)で、創始者としての役割は果たせませんでした。多くのアイディアは出したものの、体系化して後進に継承することができませんでした。どうせ天才なんて、生まれつきの能力なんでしょーー。そう考えている人をハッとさせるような、面白さと学びが凝縮されているストーリーです。
レオナルド・ダ・ヴィンチの残した合計7200枚のメモやノートを丹念に調べ上げて、この15世紀のイタリアに生まれた天才が、まともな学校教育をうけず、どうやってアート、音楽、建築、光学、土木工学、気象学、天文学、解剖学などにまたがる才能を花開かせたのか、リアルな人生を描いている伝記『レオナルド・ダ・ヴィンチ』(ウォルター・アイザックソン著)が発売されました。
合計800ページ近い大作を読んでわかることは、一見するとムダとしか思えないような好奇心が、まるで星座を形づくる星と星のようにつながり、最後はすばらしい『結晶』となっていることです。なぜ彼があんなに美しい絵を描けたのか、なぜたった十数枚しか絵画を残せなかったのか、始めてその理由を知りました。
ちなみに筆者は、アップル創業者のスティーブ・ジョブズの伝記を書いた、世界的なベストセラー作家です。私はもともとジョブズの伝記を読んで大ファンだったのですが、どの時代でも「アート」と「テクノロジー」の垣根をこえて融合させた人物が、イノベーションを生み出してきた理由がさらにはっきり理解できました。
そしてダ・ヴィンチというメモ魔が残した、素晴らしいスケッチやノートの一部も、ぜひご一読ください。すぐ役には立ちませんが、豊かに生きるためのヒントが詰まってます。大人に「大きくなったら何になりたいの?」と聞かれ、
「科学者で芸術家で、世の中にないものも作り出して、歌舞伎にも出て、探検もして、作家にもなって、マンガも描いて、探偵もしてYOUTUBERにもなりたい」と答える多動な息子。
「その中でどれか一つは?一つを決めて具体的に調べるといいよ」とか言われると、
「うーん…」と納得がいかない彼の憧れは「レオナルド・ダ・ヴィンチ」。
今夜この記事を読んであげようと思います!!
学問も興味も全ては繋がっている!!
面白い事、追求したい興味を捨てる必要はない。