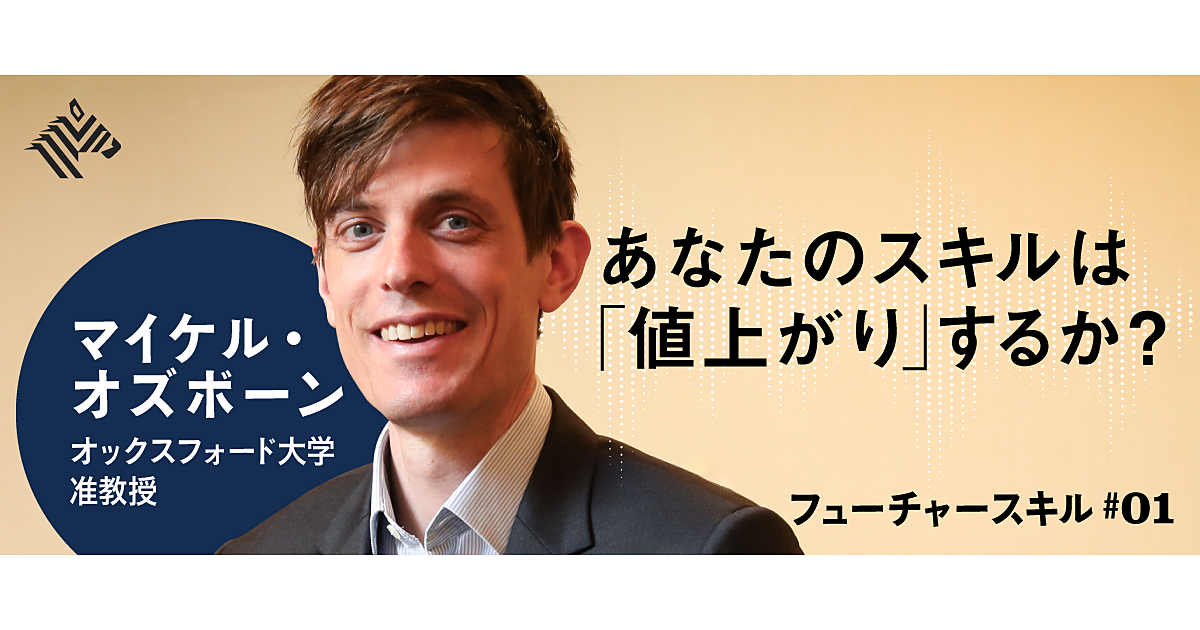【未来予測】10年後に「売れるスキル」「廃れるスキル」
NewsPicks編集部
6271Picks
コメント

注目のコメント
仕事を続けながら、NPOに関わることをお薦めします。
まずNPOの多くは弱者支援のために行いますから、人についての理解が欠かせません。また取り組む社会課題の歴史や背景、制度を学び続けることが必要であり、解決に向けてはシステム思考が必要です。
私の場合は、復興、防災、地域活性化、農業といった課題を扱っていますが、学び続けることが欠かせません。経営コンサルタント時代に特定企業の特定テーマだけを追っていた時代よりも、遥かに自分の引き出しが増え続けていると感じています。キーワードは「人間を理解する力」と「学ぶ力」。
かつて「10年後に今の仕事の半分はなくなる」と予測して、一躍有名になったマイケル・オズボーン氏ですが、最近の論文では、予測をブラッシュアップして「仕事そのものは残るが、求められる『スキル』が変わる」と述べています。
狭い意味での「プロフェッション」にこだわらず、汎用性の高いスキルを身につけることが、今後10年の生存戦略になると語るオズボーン氏。氏の論文がはからずも広めた「悲観論」をはねのける、ポジティブな提言にあふれたインタビューです。マイケル・オズボーンさんの印象は驚くほど気さく。写真撮影でも自ら「チーズ!」と言って我々を和ませてくれた後、「ゴルゴンゾーラ!」「ゴーダ(英語の発音はほぼグーダでした)」などチーズの種類を続々と言って笑わせてくださいました。これこそ10年後も(おそらくその先も)必要なソーシャルなスキルかと感じ入った次第です。