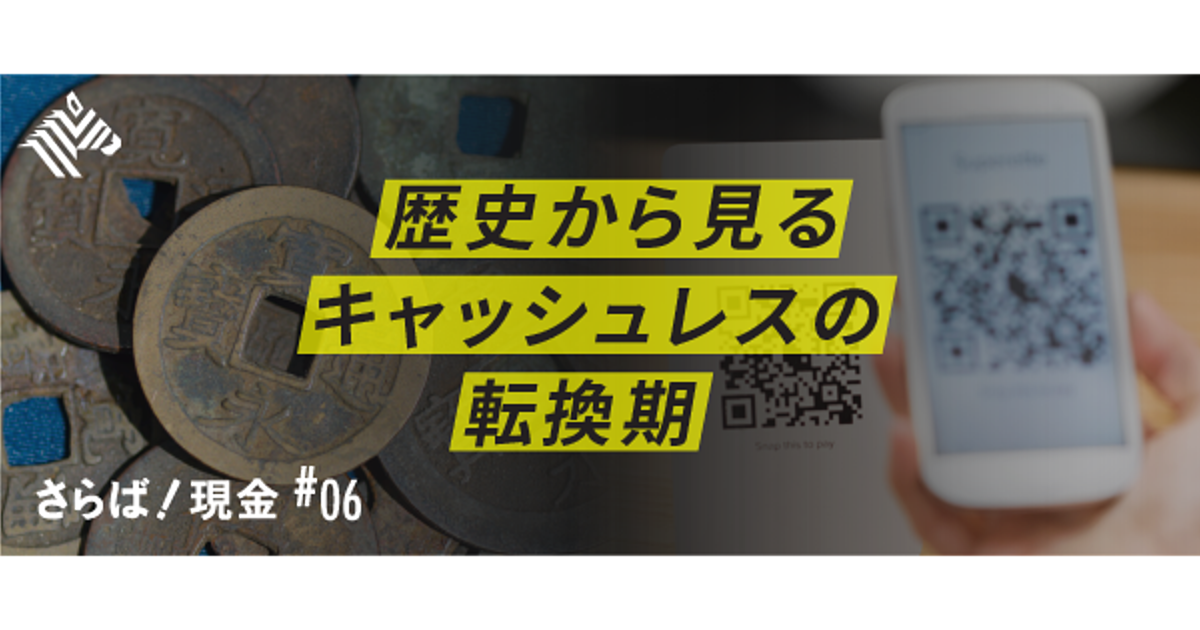【近未来】アリペイが「基軸通貨ドル」と対抗する日
コメント
注目のコメント
新書1冊分の情報が詰まっています。本日は、長年電子マネーやブロックチェーンを研究されている国立情報学研究所の岡田仁志准教授による「キャッシュレス時代の貨幣論」的な力作をお届けします。
先生には、8年ほど前からなにかと取材をさせていただいて、今回も3時間ほど(!?)お話をさせていただきました。そこで面白かった内容を私がたたき台を作り、何度も往復しながらできたのがこの原稿です。日宋貿易から満州中央銀行、金本位制、ニクソンショック、ブロックチェーンまで含めて「○○ペイ」を考える力作です。
新書でも読む感覚で、イスにでも座って読んでいただければ幸いです。とてもよく通貨の進化の要諦がまとめられています。
仰る通り、今のキャッシュレスの議論は、あくまで法定通貨のインターフェイスが、紙からプラスティックカードや非接触やQRコードに変わっただけです。
The Updateでも申し上げましたが、お金はその時代時代のテクノロジーの進化に合わせて、進化してきた歴史がありますから主流が紙から変わるのは時間の問題だと思っています。
本当に面白いのは、更にその先、中央銀行が保証している現在のお金というものが、ブロックチェーン等のテクノロジーによって、在り方が変わるのかどうかだと思います。そんなことはありえないという方も多いとは思います。
でも、日本が今の形になったのもたかだか150年くらい前からですから、私達が生きている間に大きな変化が起きてもなんらおかしくないですよね。
お金の進化を追いかけるのが楽しみでなりません。通貨発行権は国家が持つ重要な力です。近代国家では、国家以外が通貨を発行できたことはありません。というより、通貨発行権を独占することで、近代国家は近代国家でありえてきました。
「いま世界では、貨幣への昇格をめぐって、あらゆる形式の貨幣的価値の媒体が競争している。見かけ上は媒体の競争でありながら、媒体にとどまらない可能性を秘めているところに、競争の本質がある。」というのが、この記事の趣旨です。具体的には、アリペイ、WeChatPayの普及による中国の通貨の台頭でしょう。
通貨発行権の奪い合いは覇権をめぐる争いです。歴史的に、覇権を持った国は、できるだけ広い範囲で自国の通貨が使用できるようにしてきました。現在の世界のほとんどの国は、自国で通貨を発行して普及させるだけの力を持っていません。米国が(一応、IMFが、というかたちをとていますが)、各国の通貨を米ドルと交換可能と保証することで、各国の通貨は価値を持てています。
LINE Payは、そのような覇権争いに乗り出しているつもりは確かにないでしょう。アリペイやWeChatPayにしても、アリババや微博自身にはそういう意図はあまりないでしょう。中国政府も、国際貿易の元決済は増やそうとしているように見えますが、人民元を基軸通貨にしていく明確な政策を持っているようにはあまり見えません。この記事に出てくる平清盛は、宋銭を日本の通貨にしようとして、後白河法皇らと激しく対立しました。中国の通貨を自国の通貨にする、という政策の是非は、貿易体制だけではなく、源平合戦まで広がっていったような重大な争点です。宋銭は銅に資源としての価値があったことと、平家が保障したことで、相当程度に日本で普及しました。これは当時の中国、南宋や元では与り知らぬことで、日本国内独自の動きでした。後の永楽通宝も、発行権のあった明よりも日本国内で独自に鋳造したり流通した面が大きいです。
通貨というのが、歴史的に欧米と東アジアでは多少異なるものであったということも重要な点でしょう。中国の貨幣は王朝の意図とは関係なく、東アジア諸国で普及してきました。今のアリペイやWeChatPayもどうも同じようなもので、少なくとも基軸通貨の座をドルから奪う、といった意図で広がっているわけでは無いように思います。