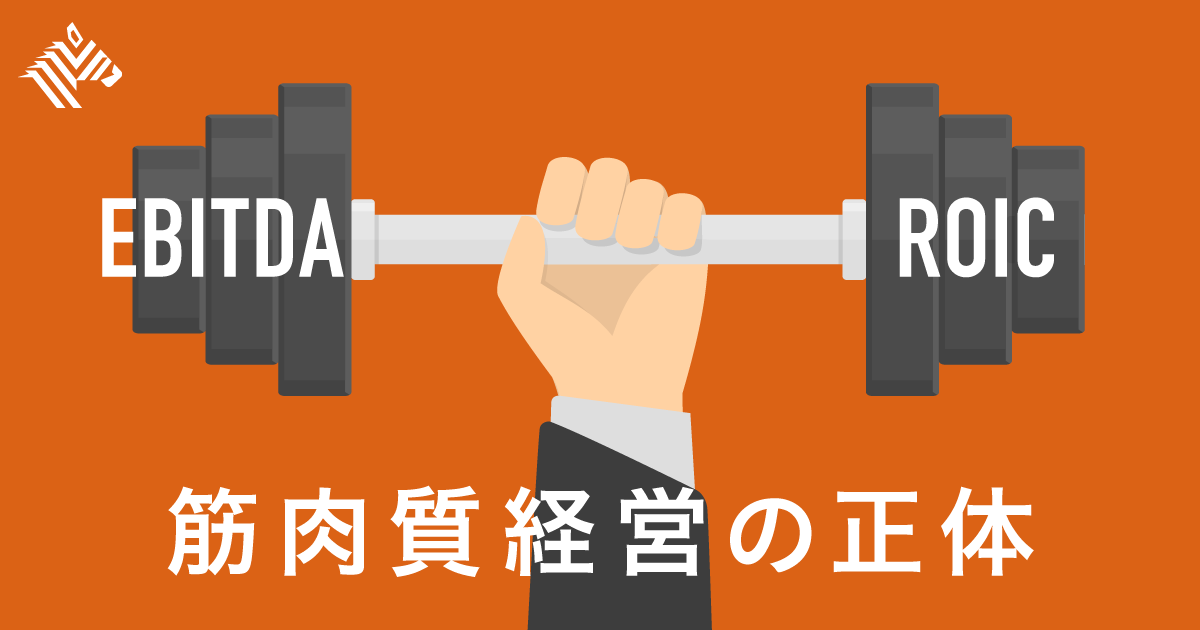
【新機軸】ファイナンス理解が10倍加速する「発想法」
コメント
注目のコメント
■EBITDA
以前からコメントしていますが、EBITDAの説明『「本業における実際のお金の増減」に近い指標』は間違ってはいないけど合ってもいないですよ。
EBITDAは確かに投資コスト(償却費)を除いた利益です。投資という行為はそれによって費用を減らすか、売上を伸ばすか、又はその両方を生み出すためのもの。それらの目的に向けて継続的に行われます。継続的に行われなければならないといった方が正しいかもしれません。
EBITDAは投資によって生じた償却費を費用から除く事で『投資した結果としての事業の純粋な伸長度合い』を測ることができる。だから利用される指標です。
(償却費は既にキャッシュアウトした費用ですので、教科書にはEBITDAは擬似的なCFを測るためと書かれていたりします。しかしこれは半分当たってて半分そうじゃないという感じです。例えばPLには償却費以外にも引当金繰入や取崩しなどの非現金費用が含まれています)
そう考えることで、記事に記載あるソニーCFOやパナCFO、旭化成のコメントの意味が整合します。
■ROIC
個人の株式投資でも、できるだけ少ない資金で買って高く売れた方が良いと思います。それと同じです。(いきなり「効率」という言葉を使うから一般の方に分かりにくい)
事業に投下した資金に対してどれだけ利益を上げたか。ROEの場合、事業に投下した資金を株主資本に限定して考えます。ROICは事業に投下した資金を株主資本+有利子負債(借金)で考えます。いずれにしても事業に投下した資金はBSの右側に出てきます。利益はPLです。
例えば借金して設備投資をしたら「事業に投下した資金」は増加します。ですからそれを上回る利益を上げなければなりません。
大規模投資を行った直後は一般的に投下資金が増加します。同時に償却という会計行為でPL利益が縮小します。それではその投資が良かったのかどうか分かりません。だからEBITDAを使って”単年度業績”を評価したりします。
EBITDAとROICのバランスというより「両方使う」という感じです。
かなり乱暴に書きましたが、概念的にそれだけ理解すれば十分だと思いますね。船井電機という企業があります。ヤマダ電機と提携して、液晶テレビブランドを展開している企業です。大谷翔平選手が所属していた時代のエンゼルスとスポンサー契約を結んでいたので、お茶の間でもFUNAIブランドを目にしていた人もいらっしゃるでしょう。
同社は2010年ごろまで、アメリカ小売大手のウォルマートなどに廉価なテレビを納めて成長するも、その後はテレビのコモディティ化を受けてずっと赤字続き。しかし、企業の存亡に関わるほどの経営「危機」とはならず、あくまでも経営「不振」の範疇にとどまりました。
今は、秀和システムの傘下となっています。
一方、かつてプロ野球オールスターのスポンサーでおなじみの三洋電機。2000年ごろは、経営トップが「なにわのジャックウェルチ」などと称されて、勝ち組に認定されていましたが。ところが、2004年の新潟県中越地震を機に、経営が一気に傾いて自力再建は不能に。
家電事業は中国傘下で、残りはパナソニック傘下となりました。
こうした違いは、決算に出てくる利益や最終損益だけを見ていても判別できませんでした(予兆を掴めませんでした)。
結局、キャッシュフロー、バランスシート、資本コストの「新・三種神器」と私が勝手に決めた指標で追わないと分からないというのが私の現時点の結論です。
今回、この考えに基づき、2つの財務指標を大胆に健康に例えてみました。NPで過去4年ほど、CEOおよびCFO、またはコーポレートファイナンスに詳しい方々に質問をしてきた結果、厳密性には欠いていても、この記事で紹介するような感覚を身に付けている人が多いという実感を得ています。上場するグロース市場の経営者と話していても営業利益よりはEBITDAで会話することが増えてきました。マネーフォワードなどは、決算短信の表紙で実績や予想にEBITDA項目を独自に設けるほどにこの指標を重視しています。
企業買収のバリュエーションになぜEV/EBITDAを用いるのかをしっかりと説明できるとファイナンス学習的には理解が進んでいるのかなという感触です。
